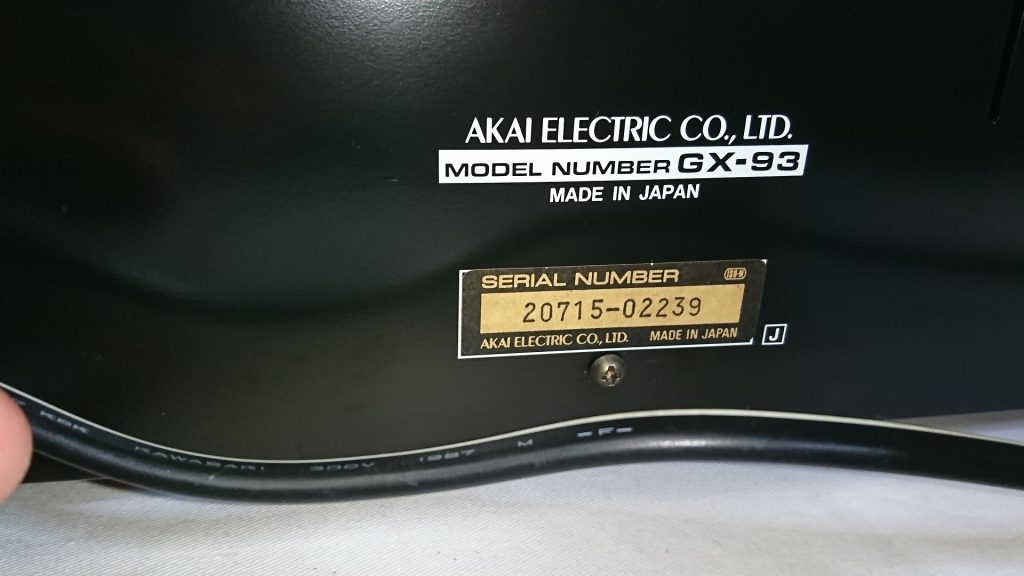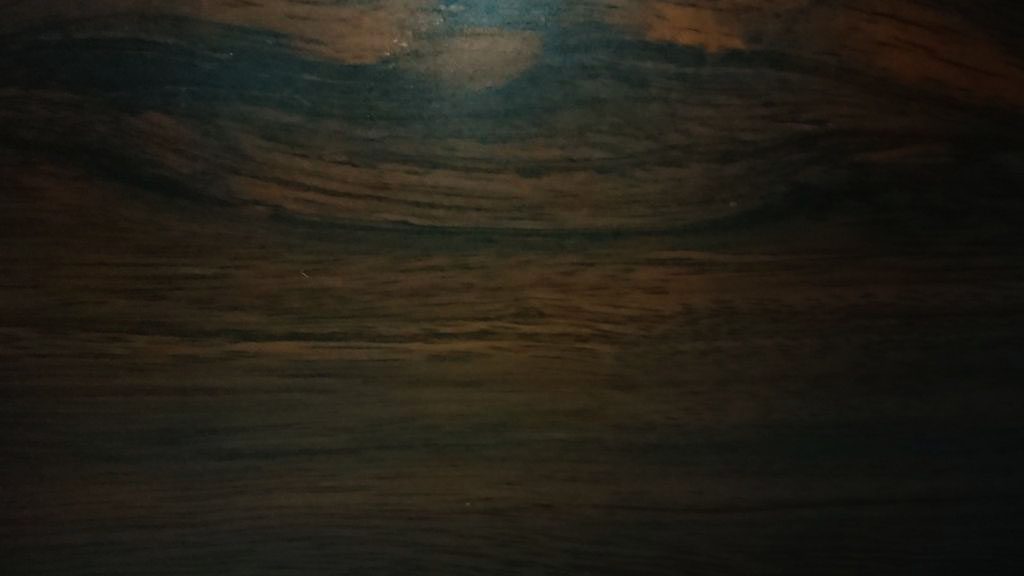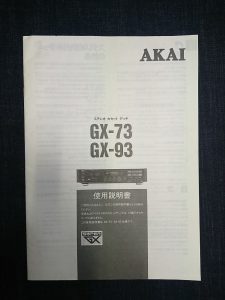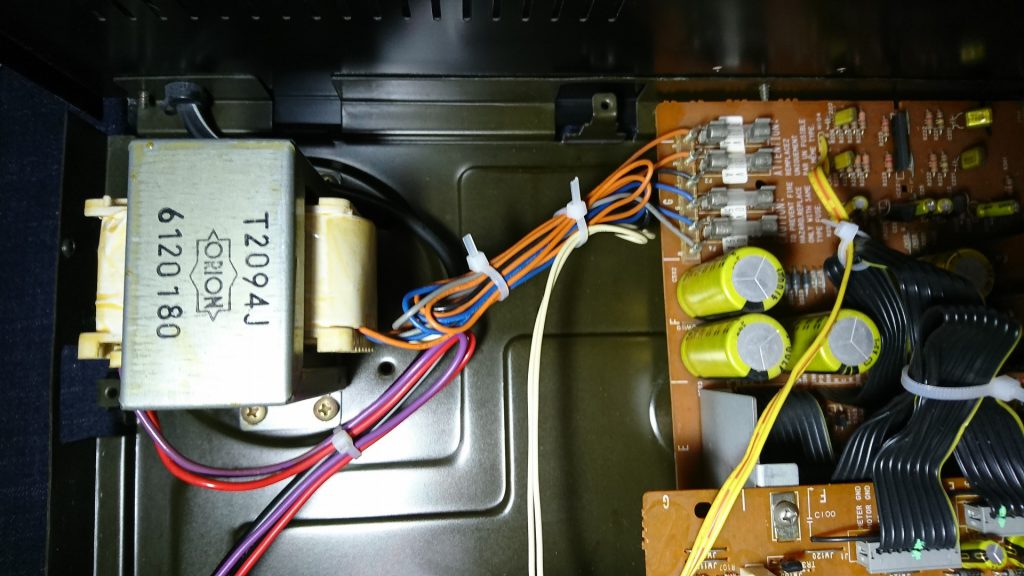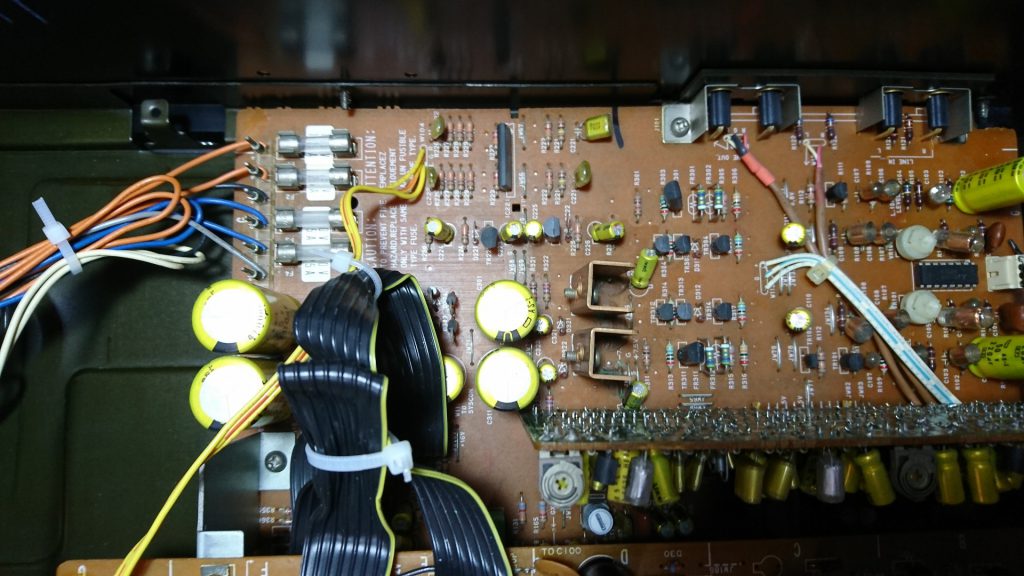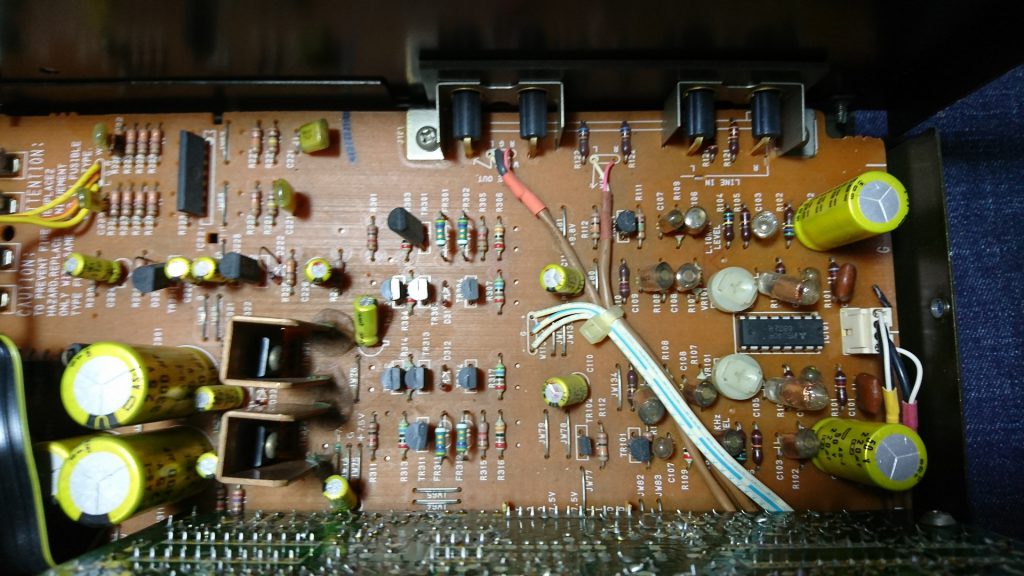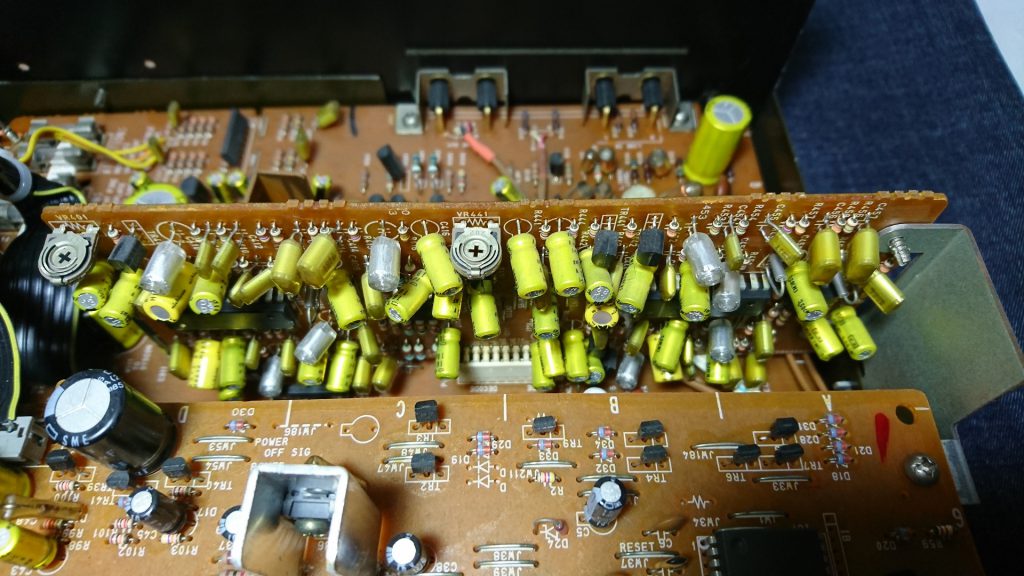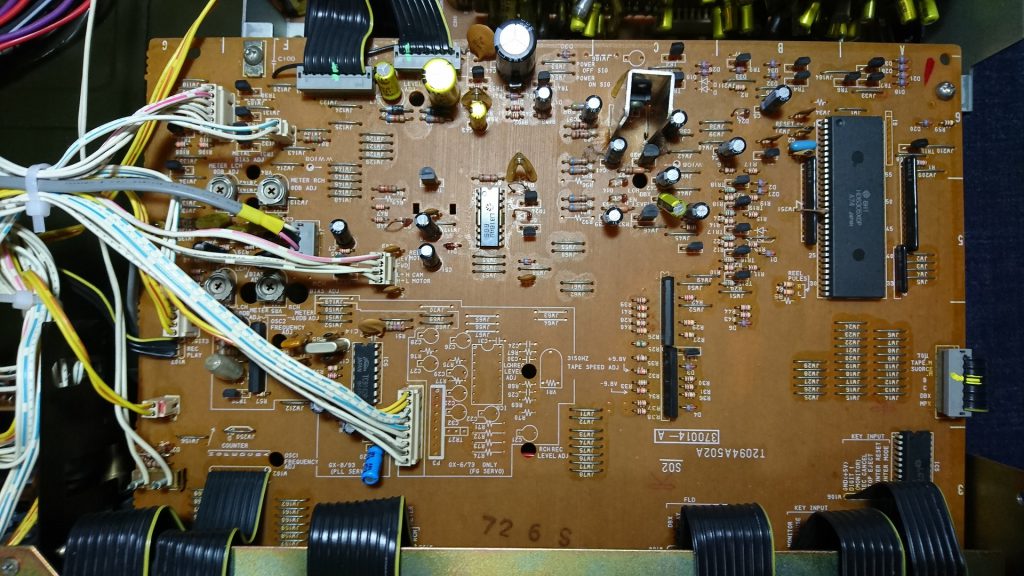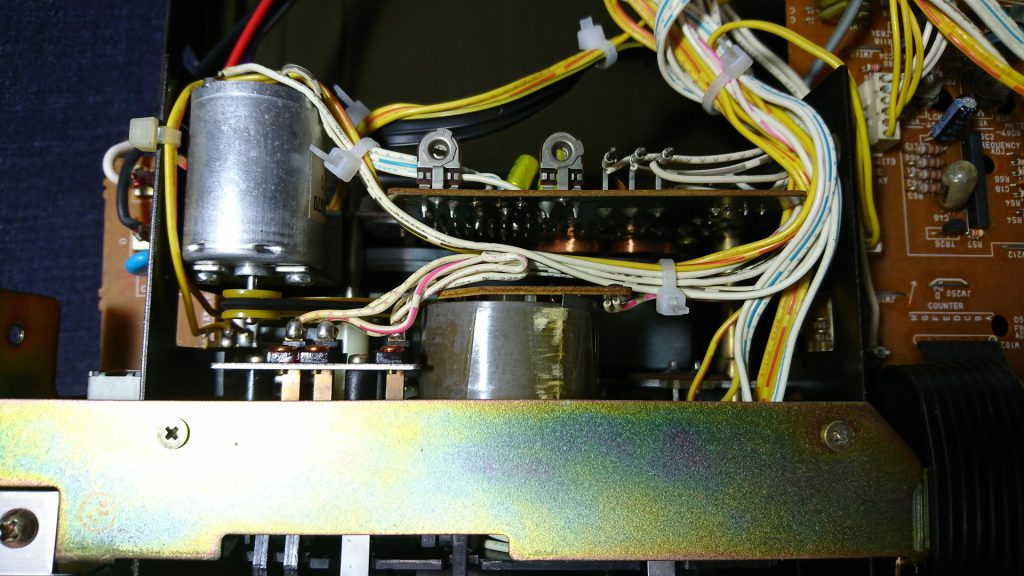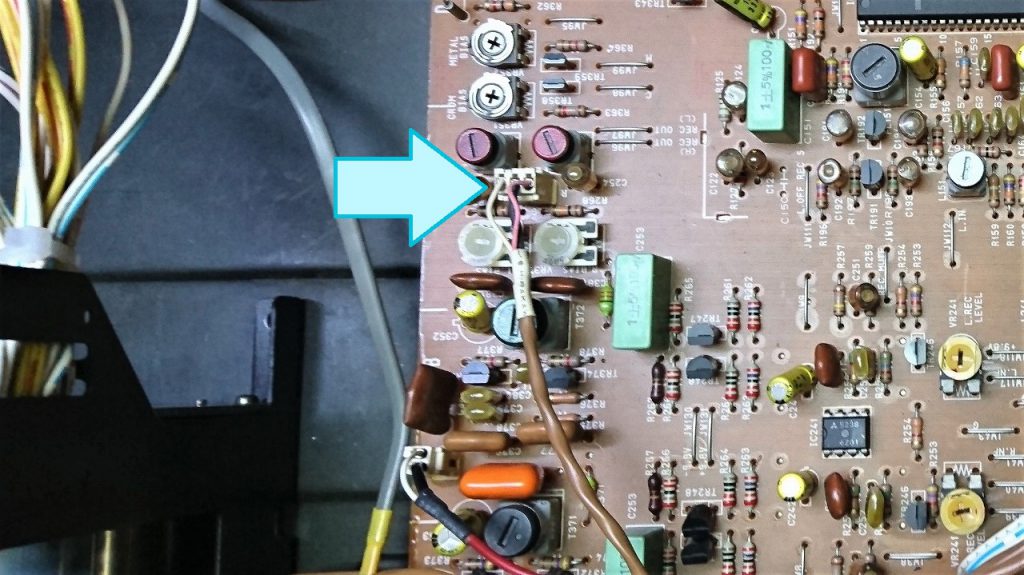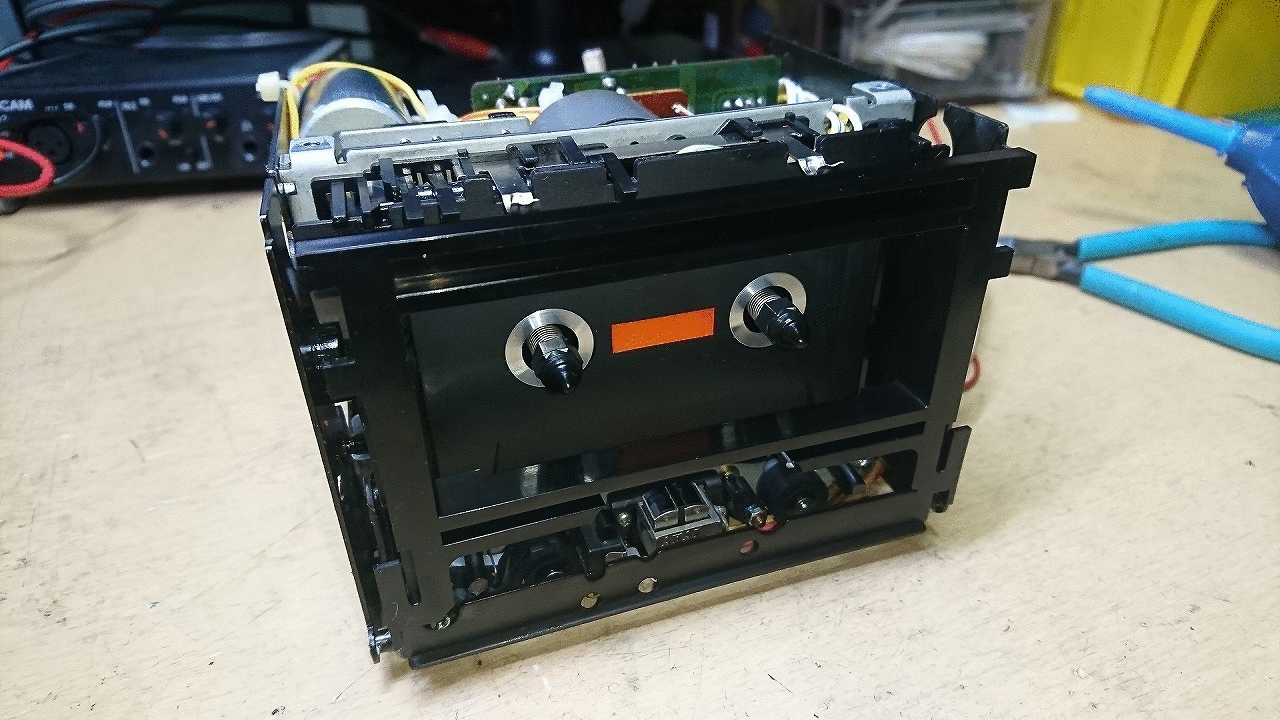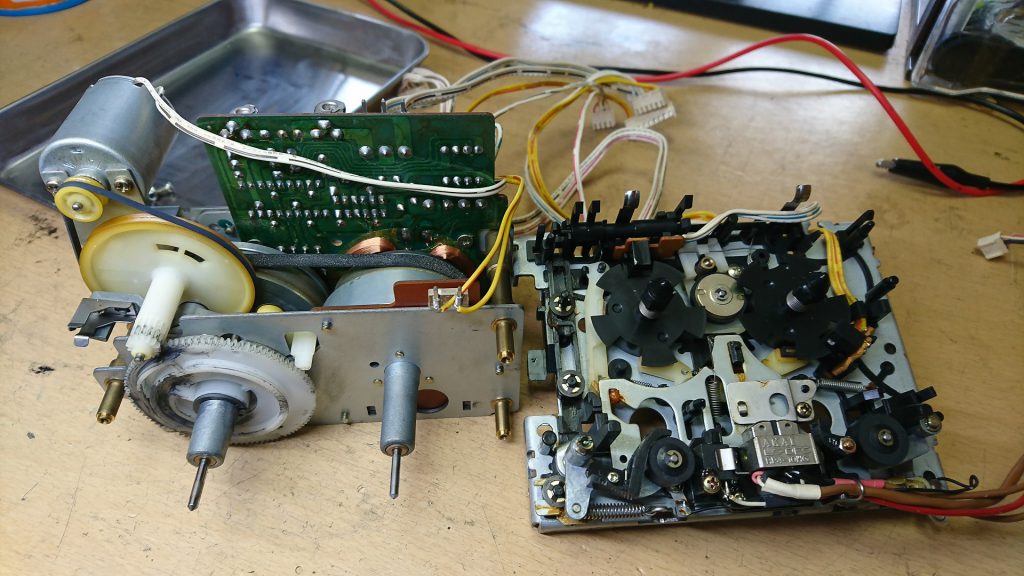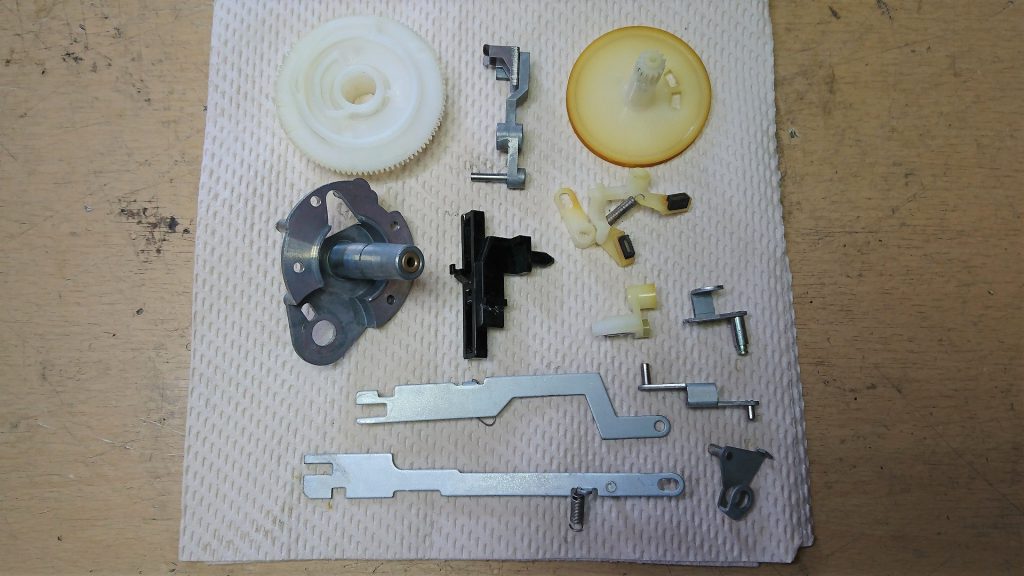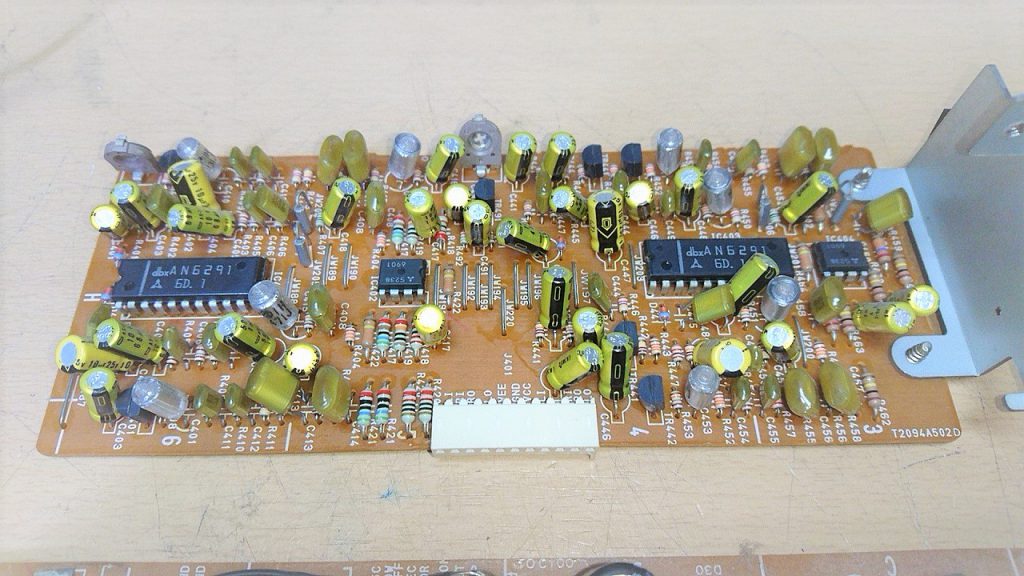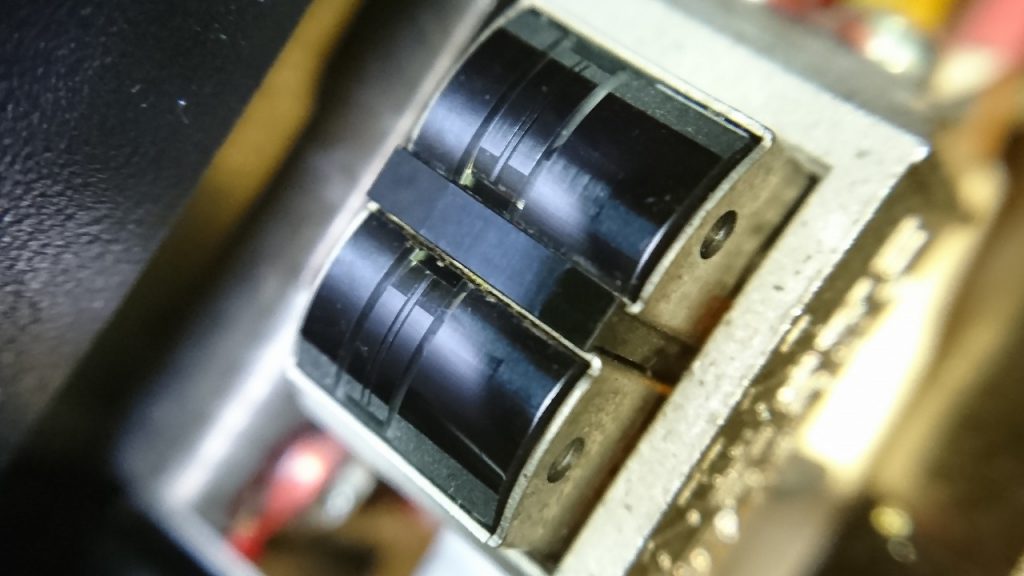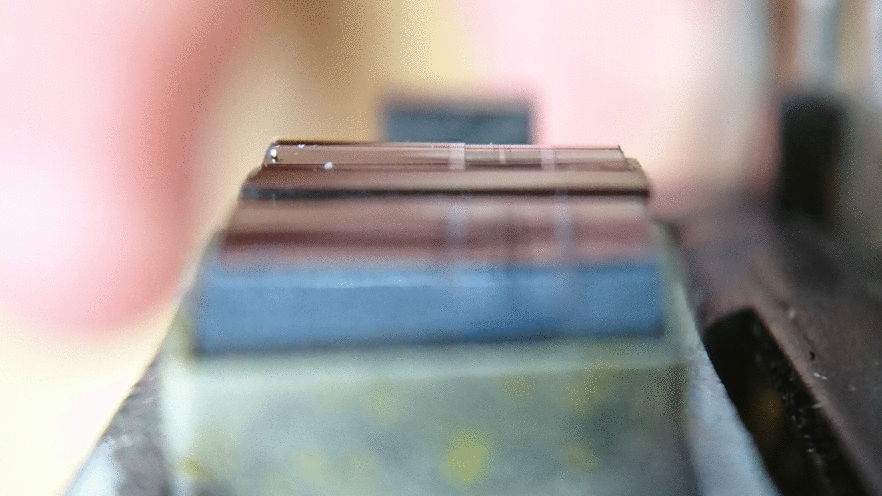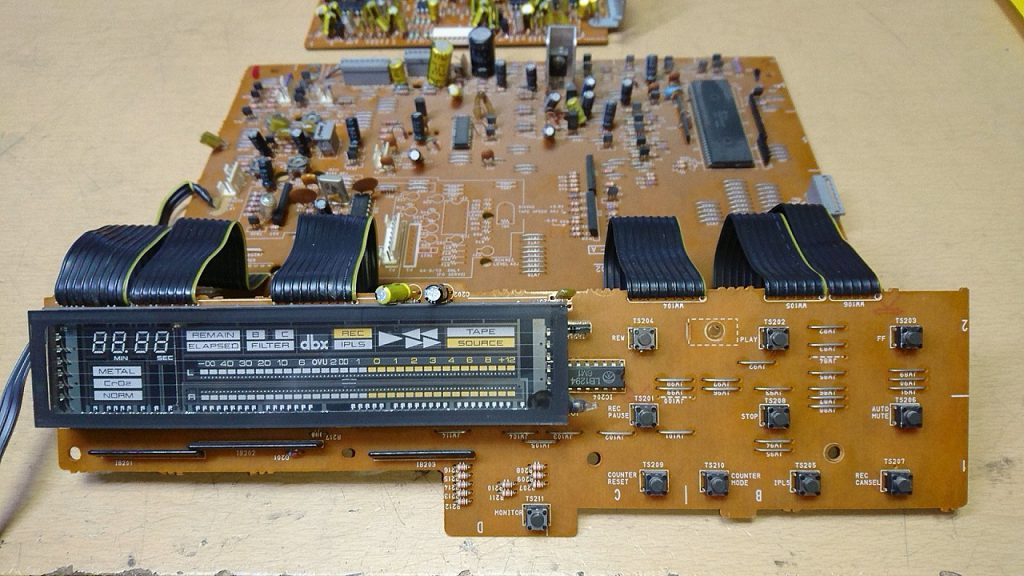概説
1986年に登場したAKAIのフラッグシップカセットデッキです。AKAIで初めてサイドウッドが装着されたモデルでもあります。薄型のボディにサイドウッドという組み合わせは、高級機としては重厚な雰囲気は抑えつつも、引き締まった格好になっていると思います。管理人自身もお気に入りのデザインです。
機能面では大幅に簡素化されました。キャリブレーション機能が無くなり、オーソドックスに録音レベル・バランス・バイアスが調整できるだけとなっています。その分、ボタンやスイッチの数も減り、AKAIのカセットデッキとしてはやや簡素な印象です。
ノイズリダクションは、ドルビーのBタイプ・Cタイプに加え、ヒスノイズが殆ど無くなるほど強力なdbxを搭載。実はこれまでAKAIのフラッグシップモデルにはdbxが搭載されていませんでした。その代わり、オートチューニングなどのハイテク機能を搭載していました。
メカニズムは、1982年のGX-F91やGX-F71などから採用されているものを搭載。テープを入れるとヘッドとテープが接触した状態で待機するので、再生ボタンを押すと一瞬で再生が始まります。録音/再生ヘッドはもちろんスーパーGXヘッド。
GX-93にはボディーカラーが2色あり、ブラックのほかにシャンパンゴールドが存在します。AKAIのシャンパンゴールドはとても希少です。確認している限り、このGX-93と、A&DのGX-W930しか存在しません。
1987年からはA&Dブランドへと変わり、外観は殆どそのままにGX-Z9000に名を改めて再登場します。しかし残念ながら、GX-Z9000になってからはシャンパンゴールドは無くなり、ブラックのみとなりました。電子回路にも若干の改良が施されていますが大差はありません。1つ大きな相違点としては背面のLINE-OUT端子のレベルを調整できるか否かです。GX-93では調整が可能です。
もう一つ違いを挙げるとしたらブランドのロゴでしょうか。AKAIが好きならGX-93、A&Dが好きならGX-Z9000です。
外観の詳細画像
デッキの内部
オープン・ザ・キャビネット

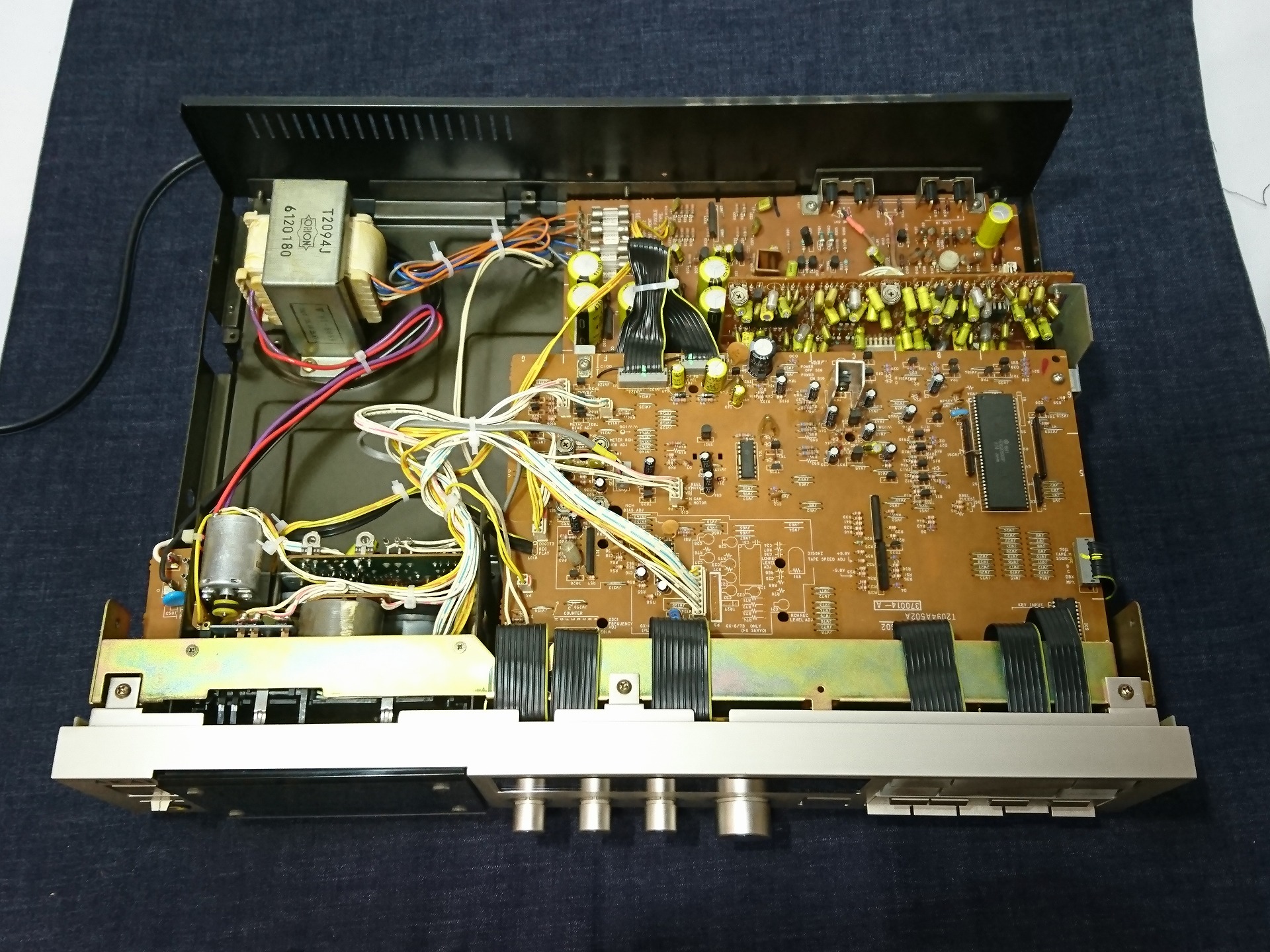
サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。
デッキの分解画像
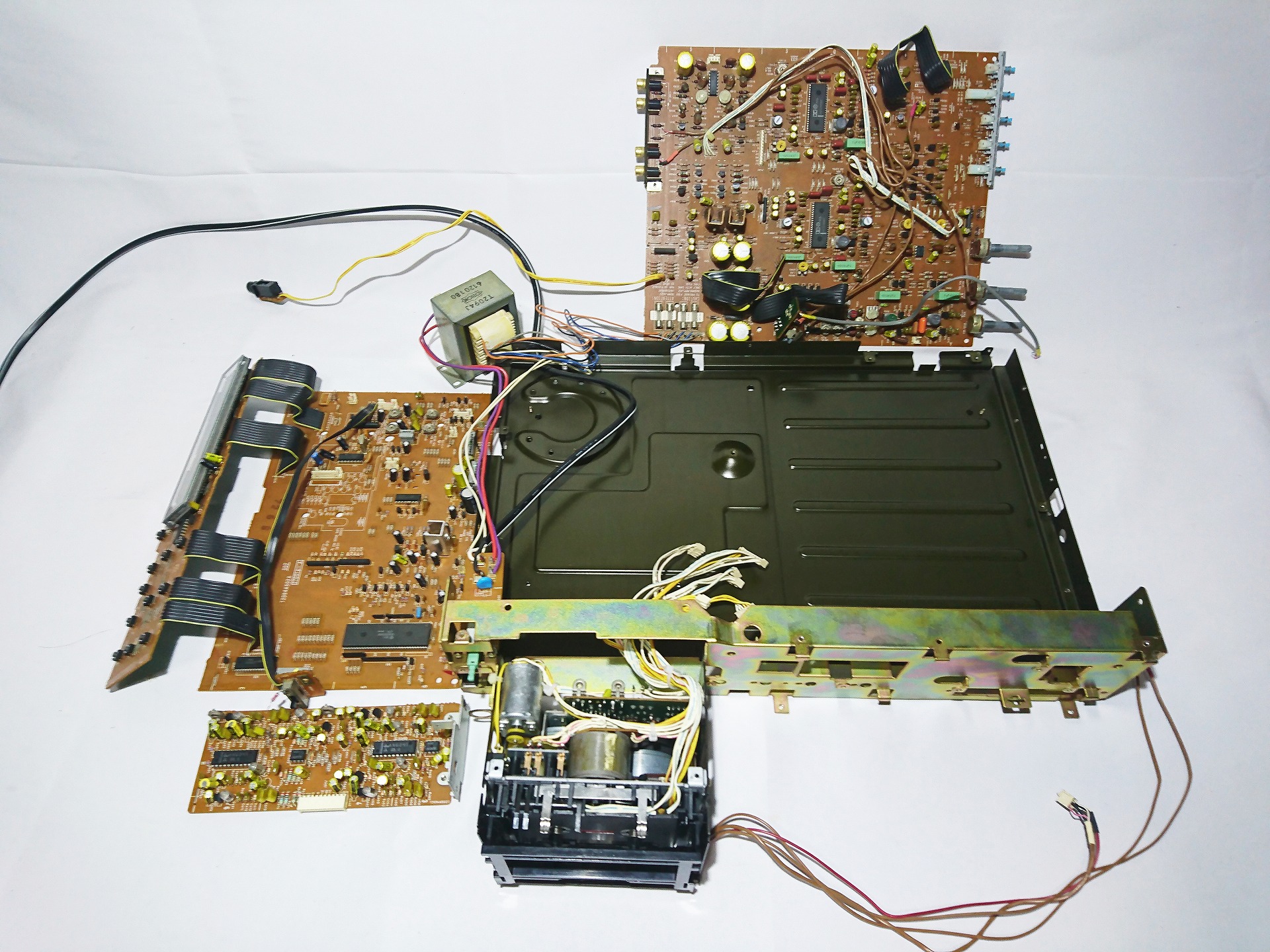
ゴールドモデル
撮影に協力してくださった方
・埼玉県 カワダ様 (1986年製の外観画像・不良ヘッドの画像 2019年2月,2021年8月撮影)
・兵庫県 「モモゾウ」さん (1987年製の画像・デッキ分解画像 2020年5月撮影)
※ゴールドモデルは当方所有デッキです。レンタルも行っています。
⇒https://nishimurasound.jp/blog/rent-gx93