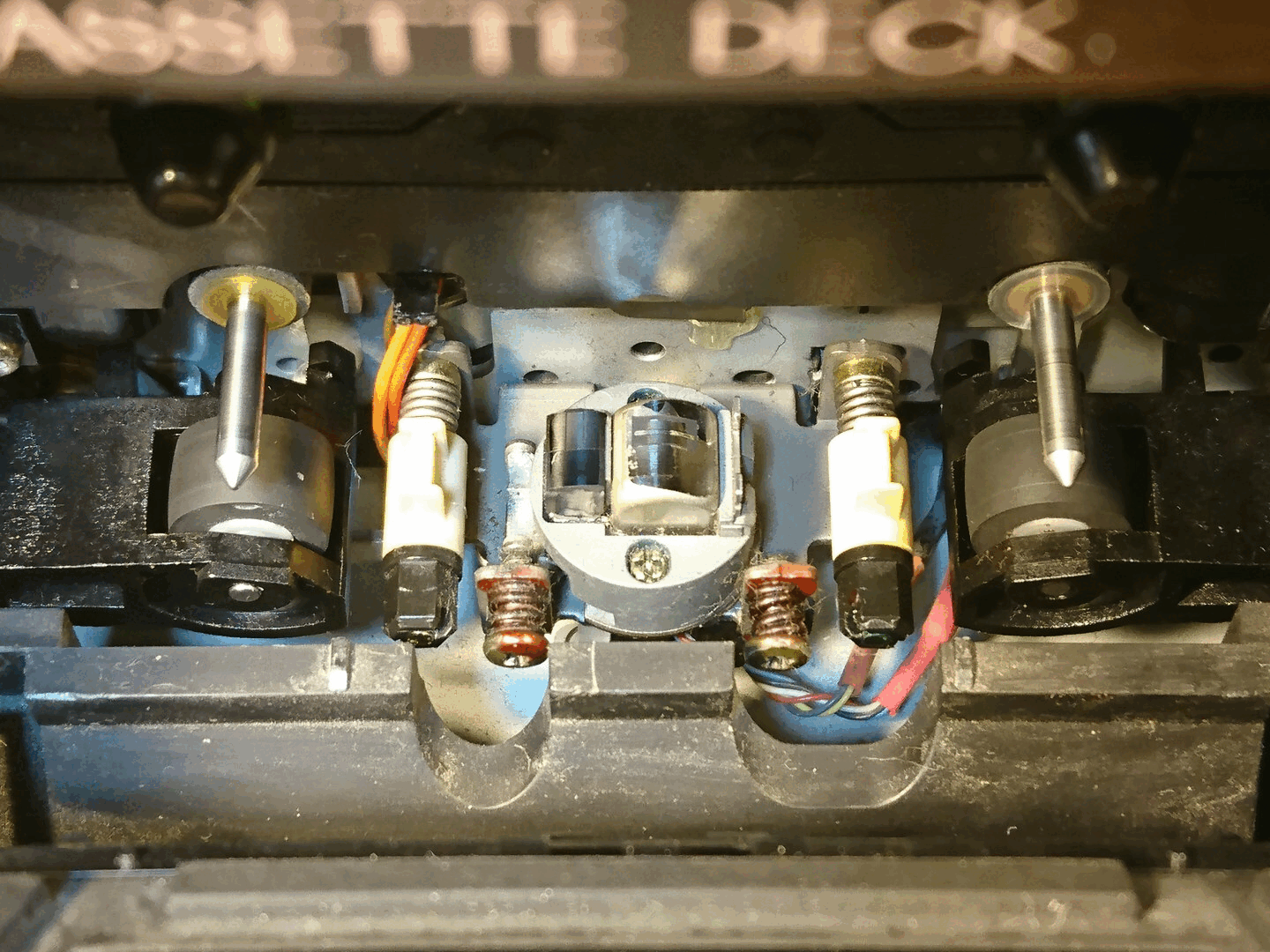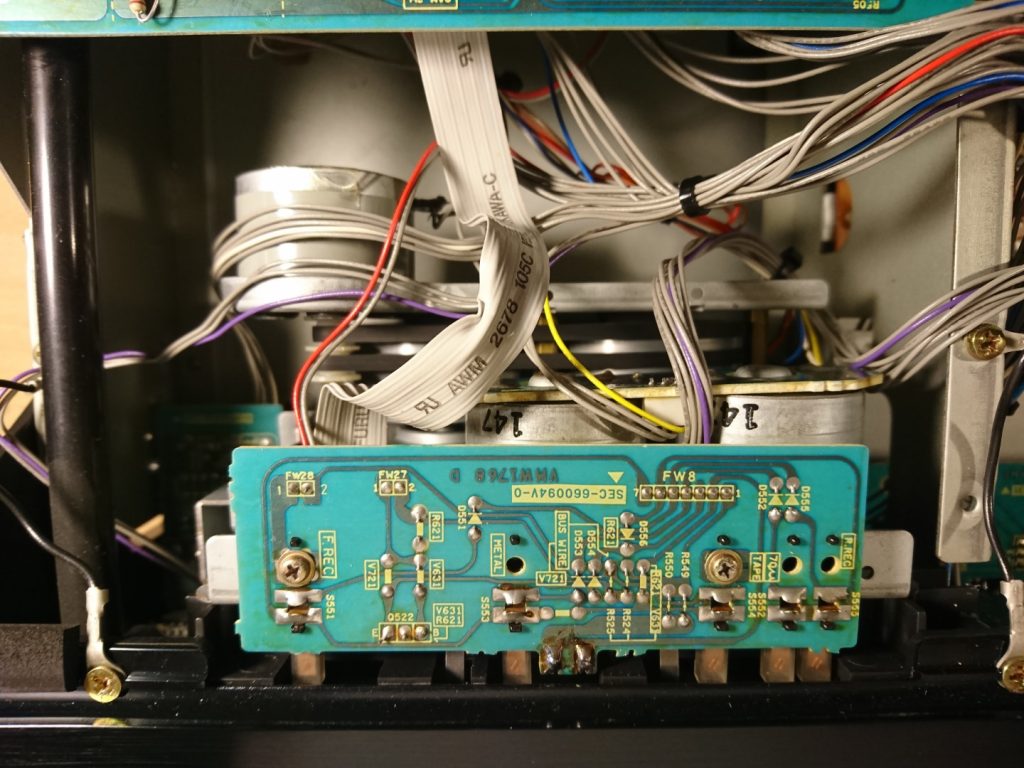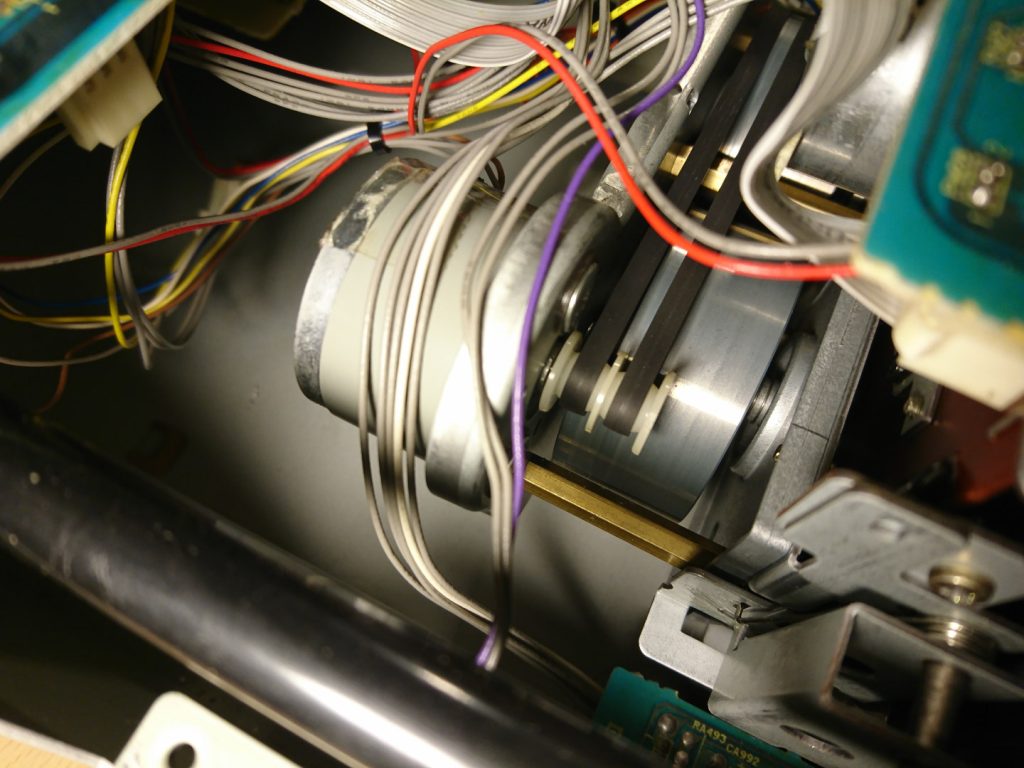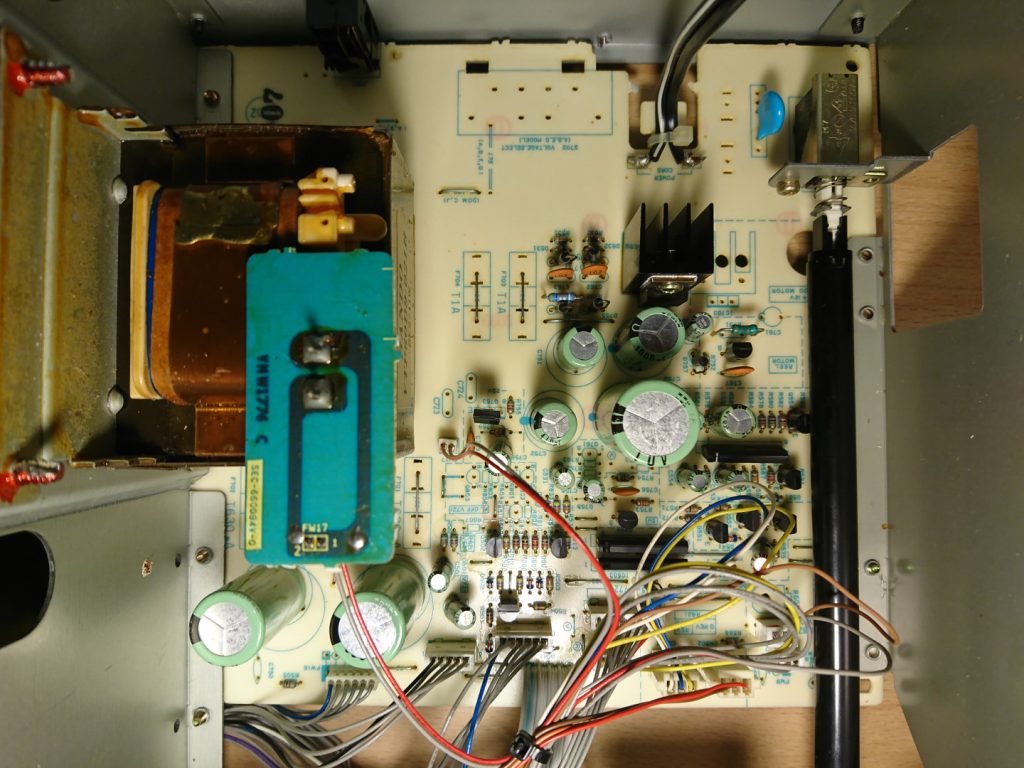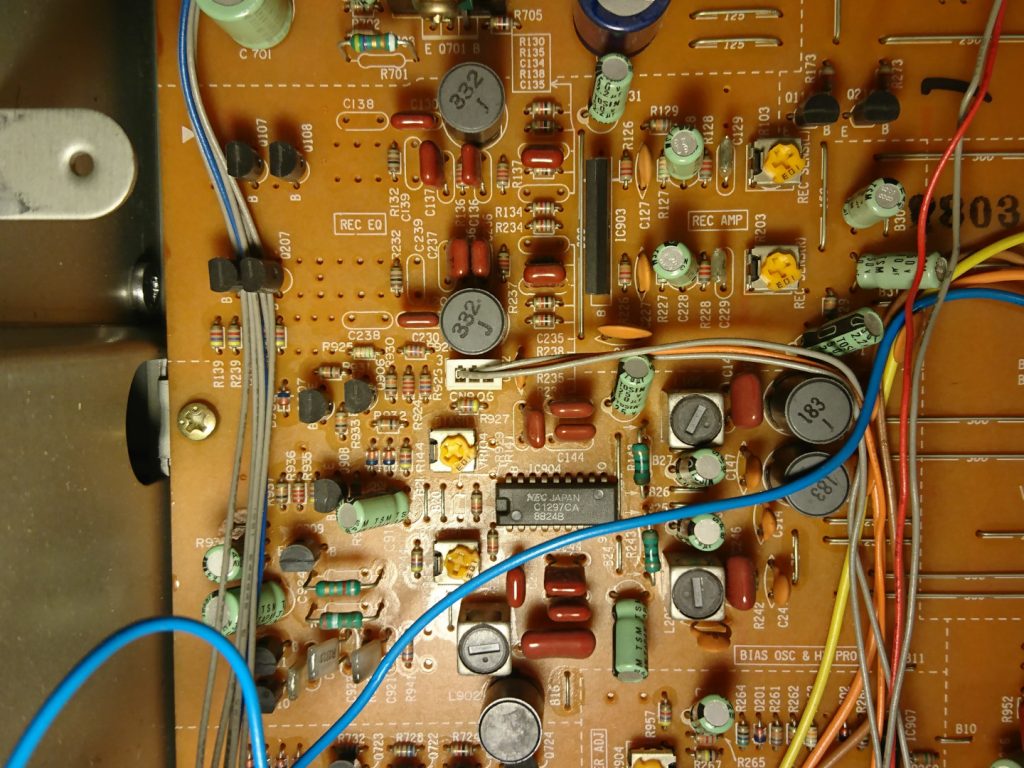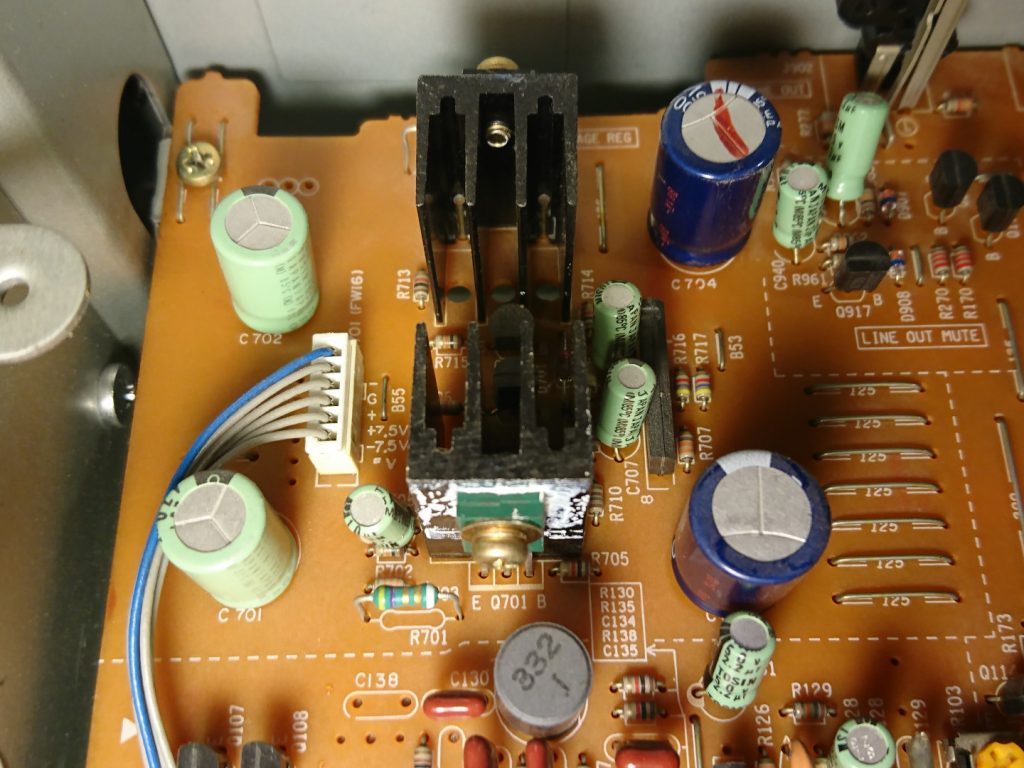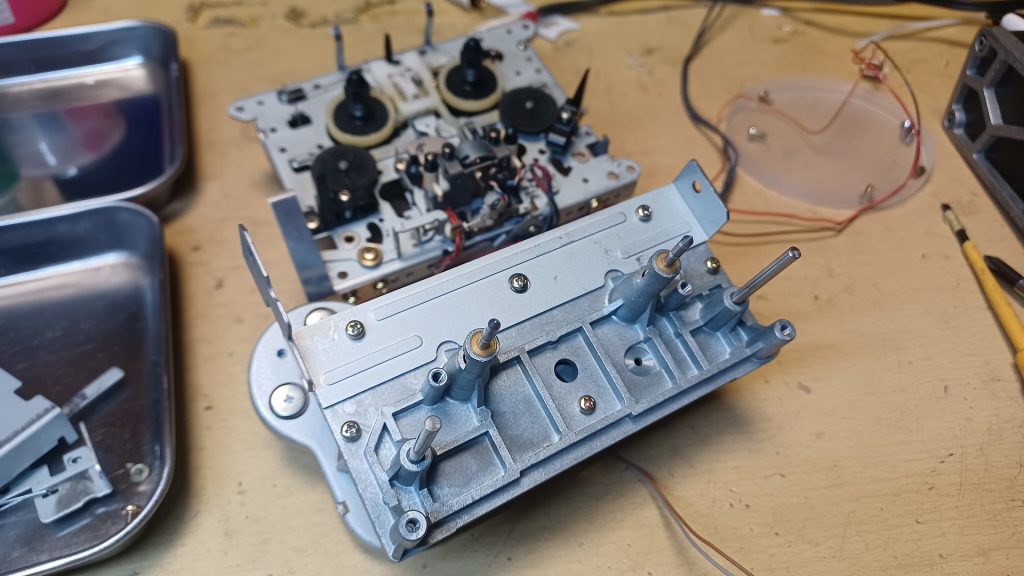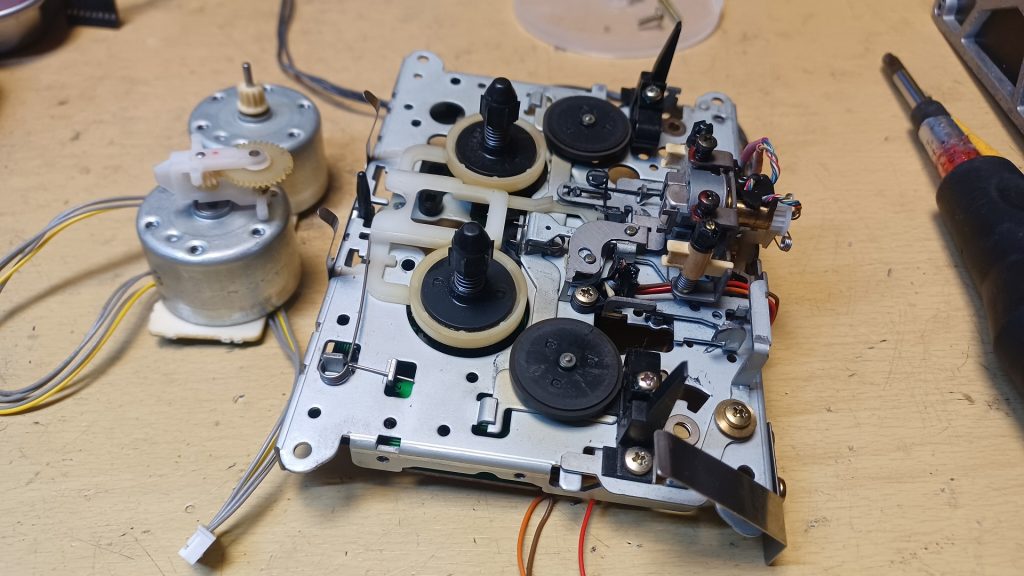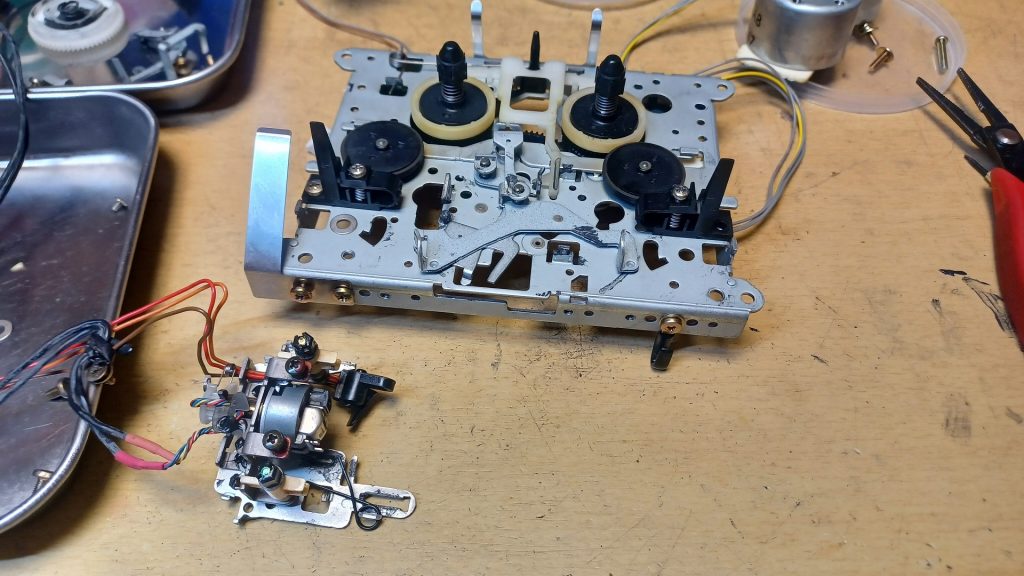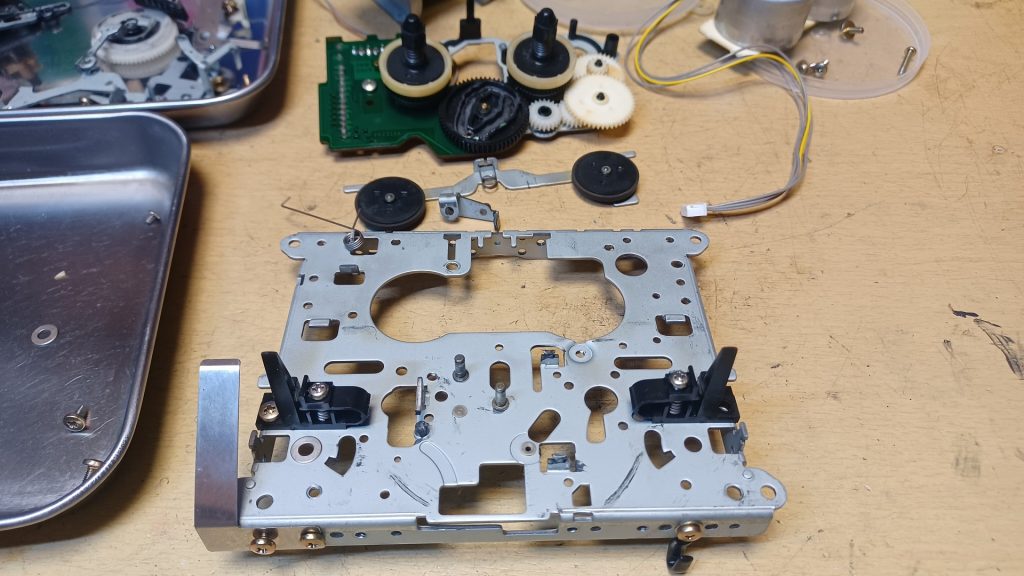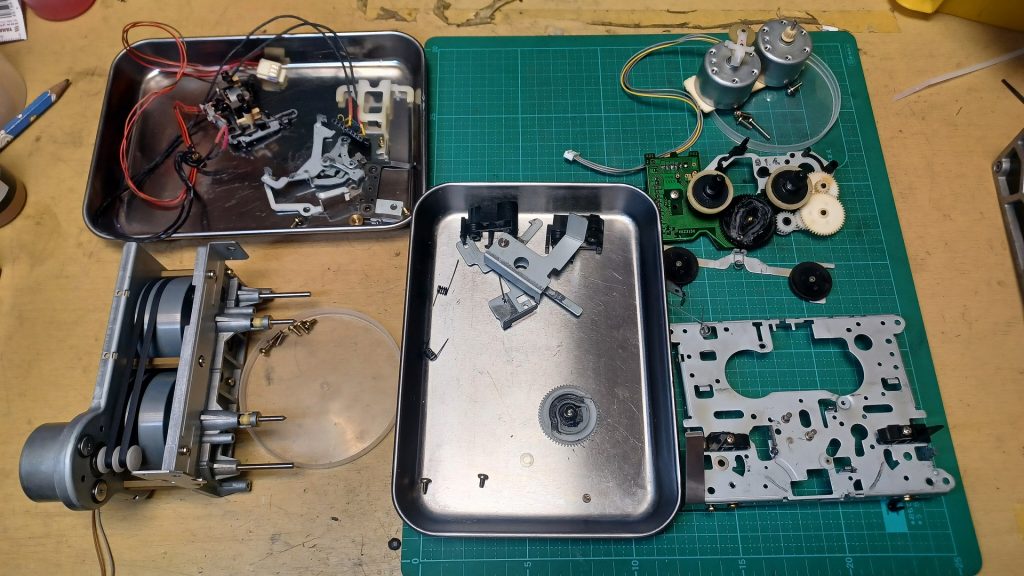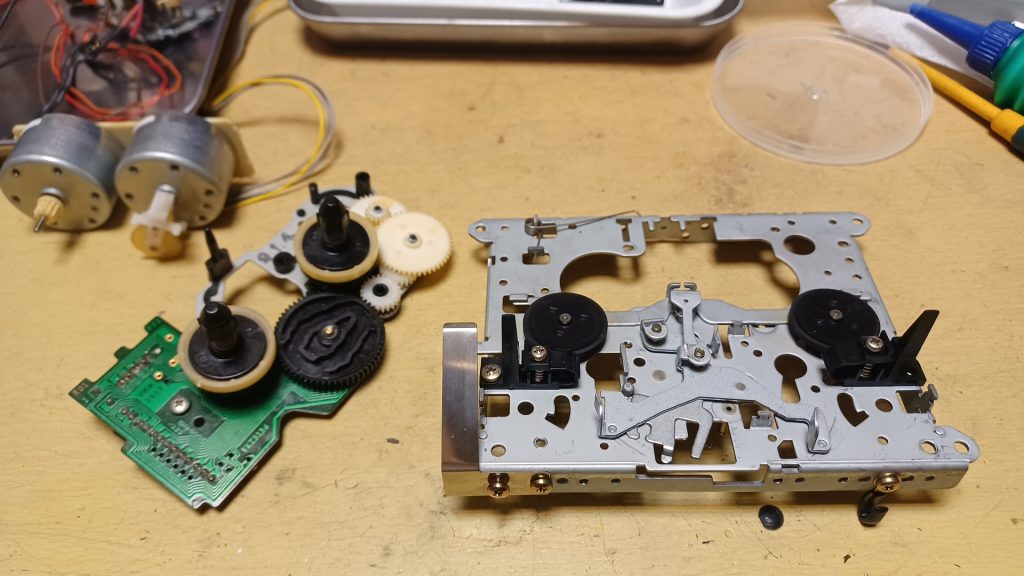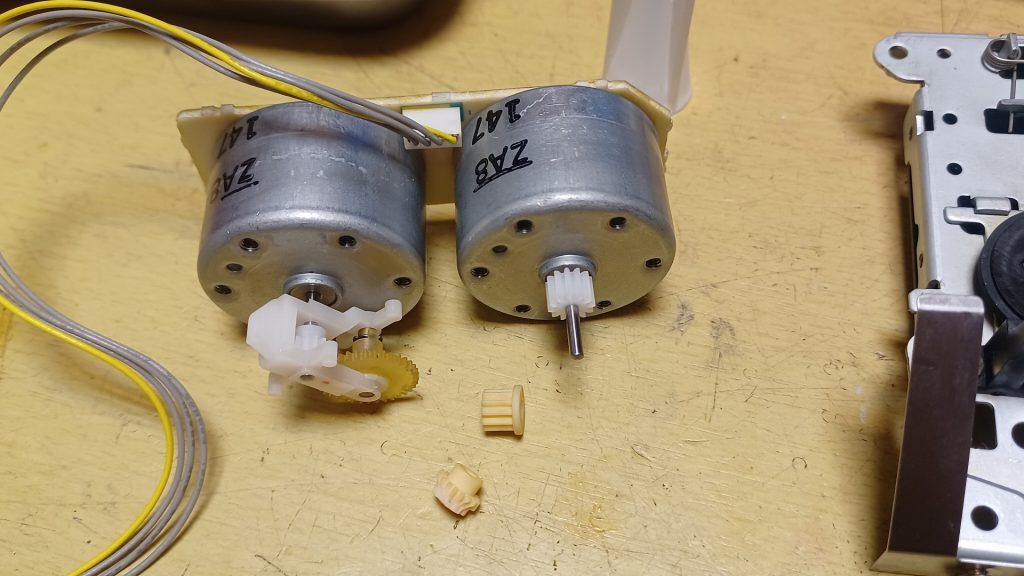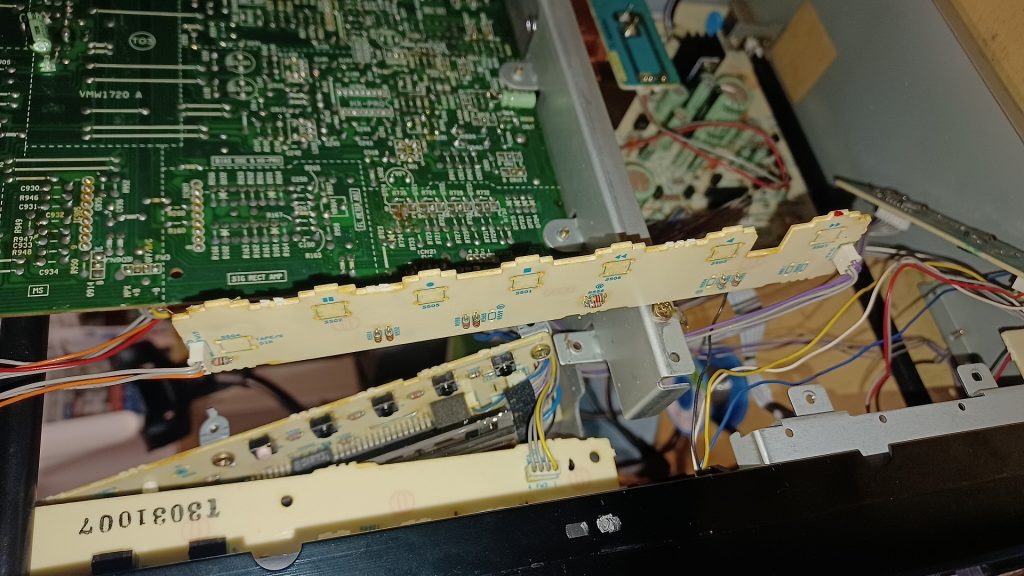ページ作成:2025/1/27
概説
Victor TD-R621の構造&搭載機能
| ヘッド | 回転2ヘッド方式(録再ヘッド:ファインアモルファス) |
|---|---|
| メカニズムの駆動 |
ロジックコントロール・カムモーター駆動 |
| キャプスタンの回転 | DCサーボモーター |
| テープの走行方式 | オートリバース |
| カセットホルダの開閉 | 手動式 |
| スタビライザー | あり |
| テープセレクター | 自動 |
| ノイズリダクション | ドルビーB/C |
| ドルビーHX-Pro | 強制ON |
| 選曲機能 | あり(前後1曲) |
| メーター | LEDピークレベルメーター(0dB=0VU 160nWb/m)・デジタルピーク表示付き |
| ライン入力 | RCA端子2系統(LINE IN, CD DIRECT) |
| ライン出力 | RCA端子1系統 |
| キャリブレーション機能 | バイアス調整のみ |
| カウンター | 4デジットカウンター、テープ残量表示 |
| その他の機能 |
|
TD-R621の特徴
○再生アンプにはFET適用のDCアンプ方式を採用(オートリバースでは少数派)
○リバース速度は回転ヘッド式にしては結構早い
○メカの基本構造は3ヘッド機と同じ
○上級機よりも音質の癖が少なく場合によっては聴きやすいことも(上級機は低音が強め)
TD-R621の関連機種
- TD-V631
ほぼ同じアンプ設計ながら3ヘッドの兄弟的存在
録音サンプル
テープ:RTM C-60(現行品)
ノイズリダクションOFF
音源:Nash Music Library
【フュージョン・ロック】容量53.0MB
96kHz-24bitのためデータ容量が多くなっています。ご注意ください。
外観の詳細画像
サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。
デッキの内部
オープン・ザ・キャビネット
画像にマウスオン(タップ)してください。

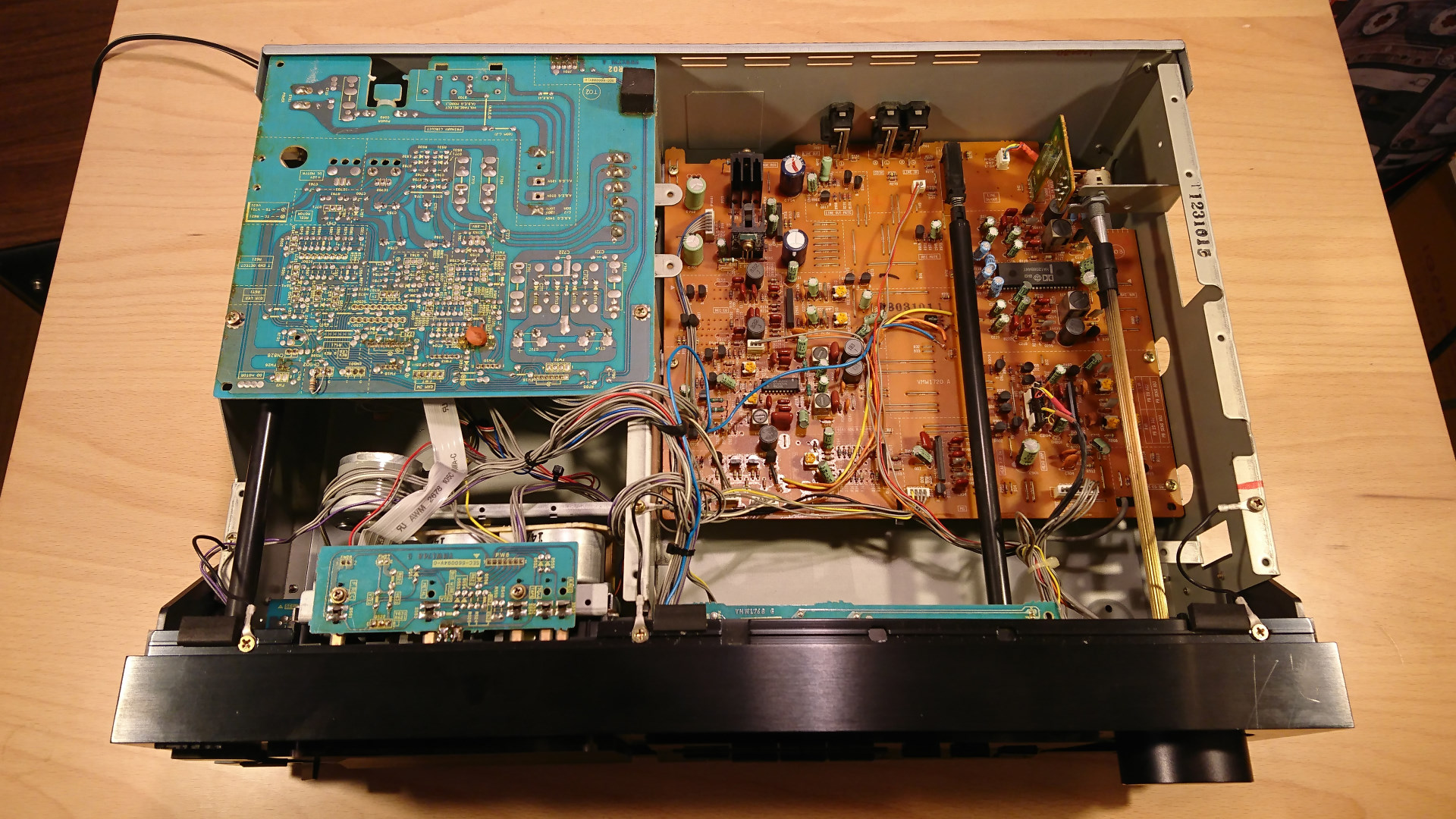
サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。
デッキの分解画像
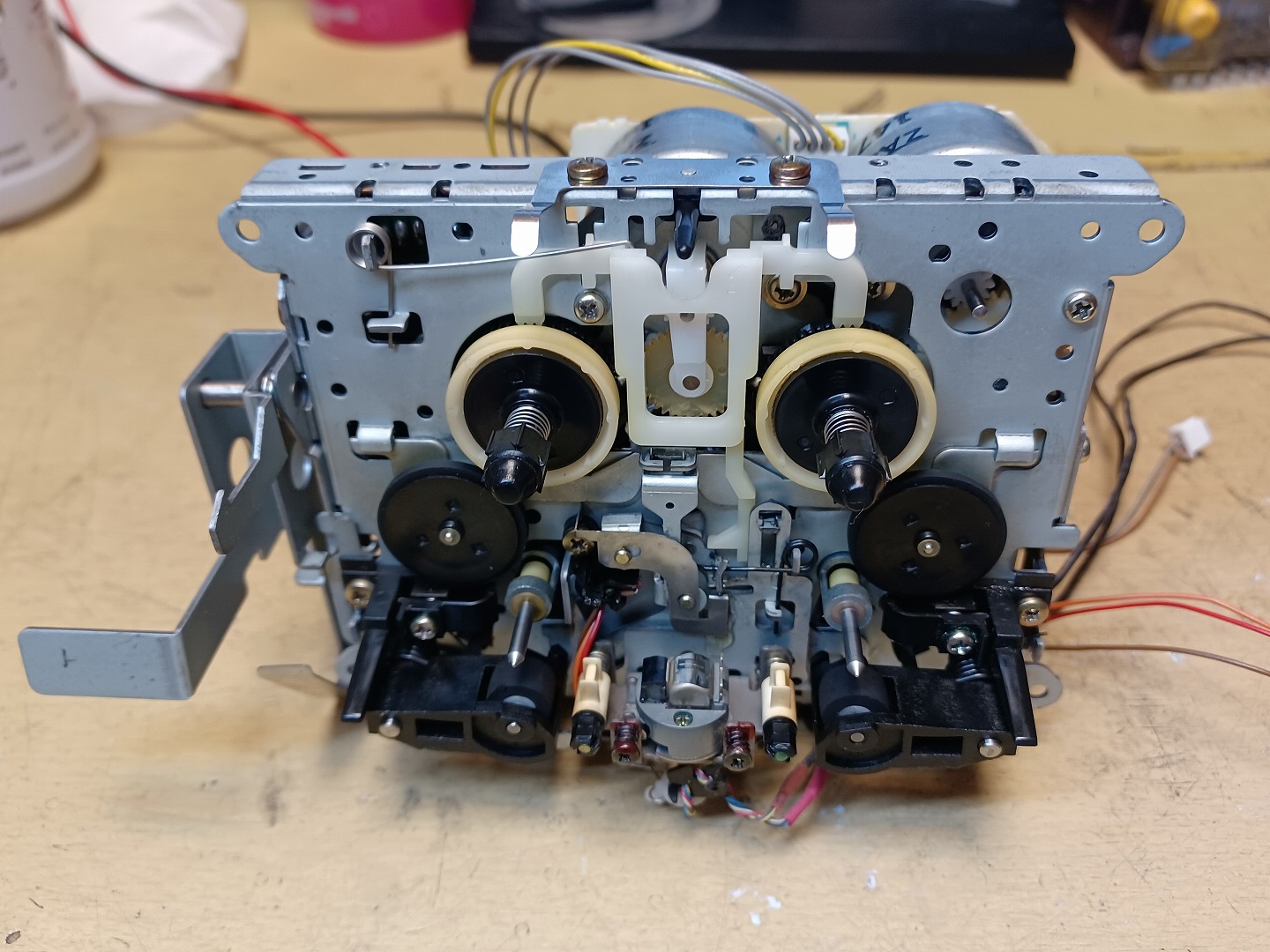
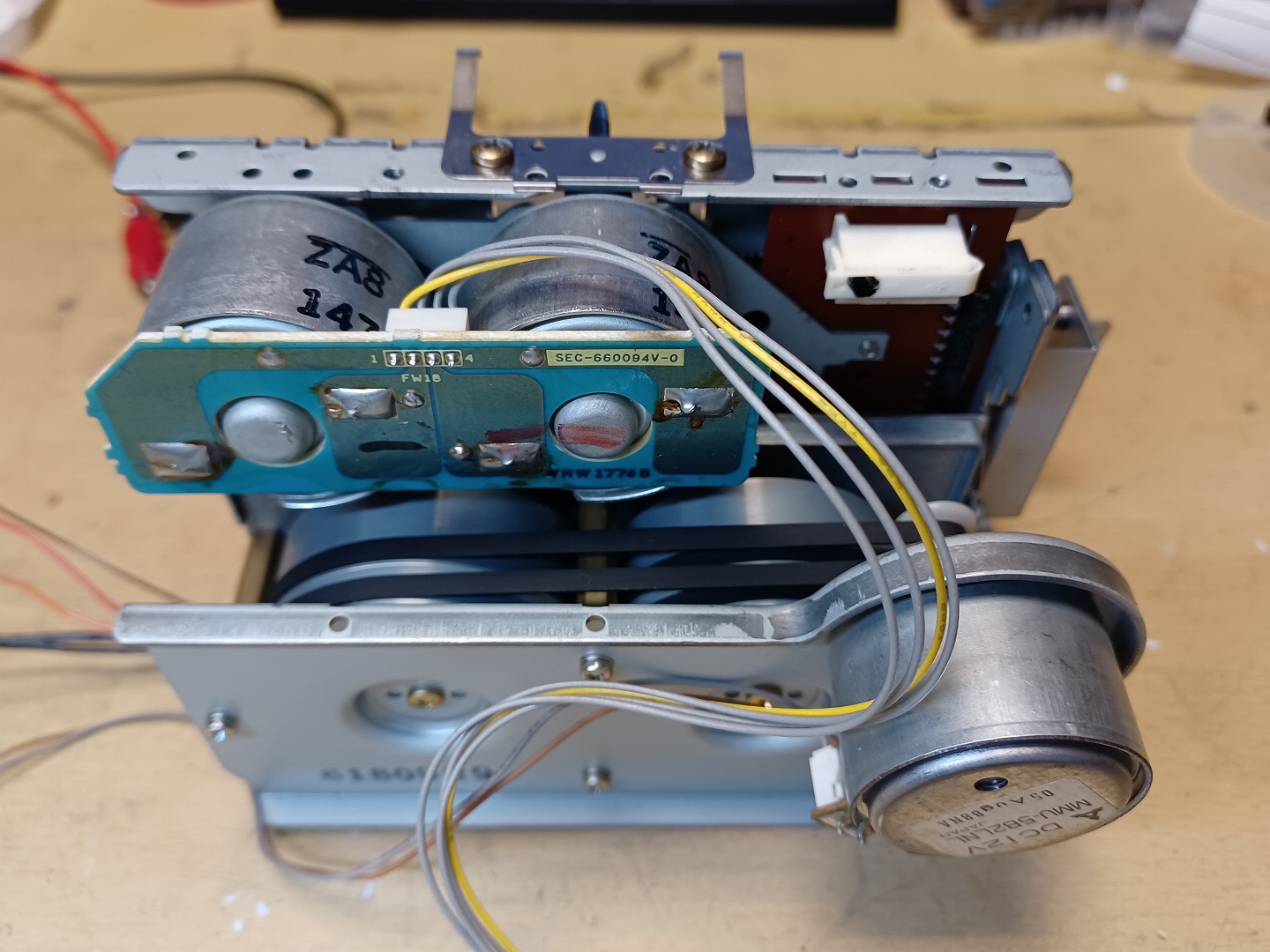
サムネイル画像をクリックすると拡大画像をご覧いただけます。
参考周波数特性
画像にマウスオン(タップ)すると周波数軸が線形に変わります。
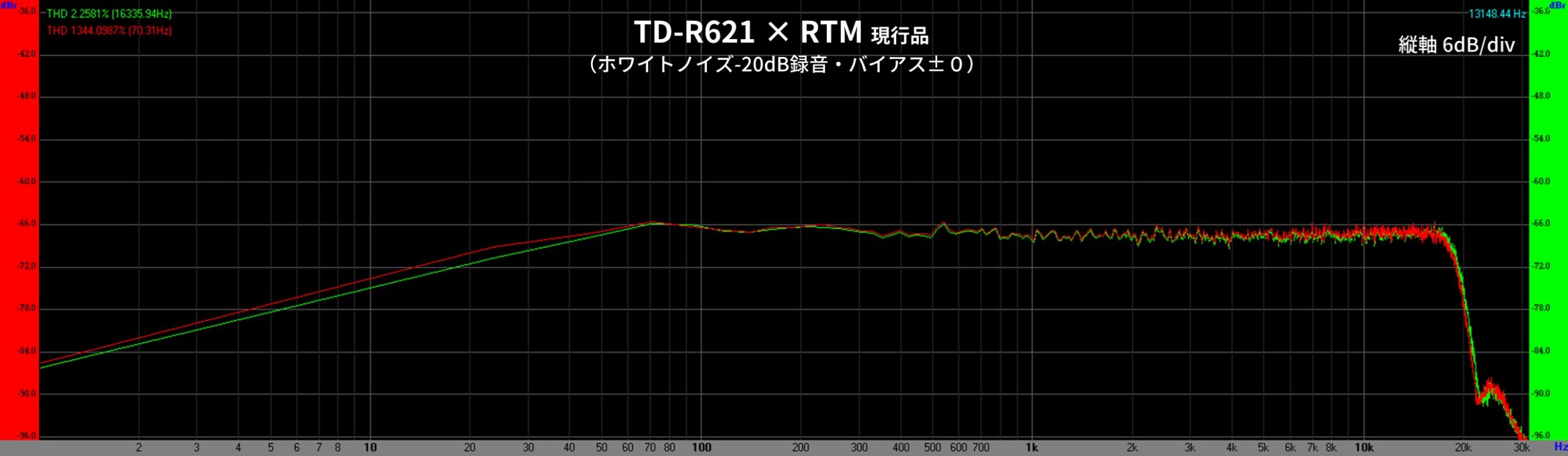
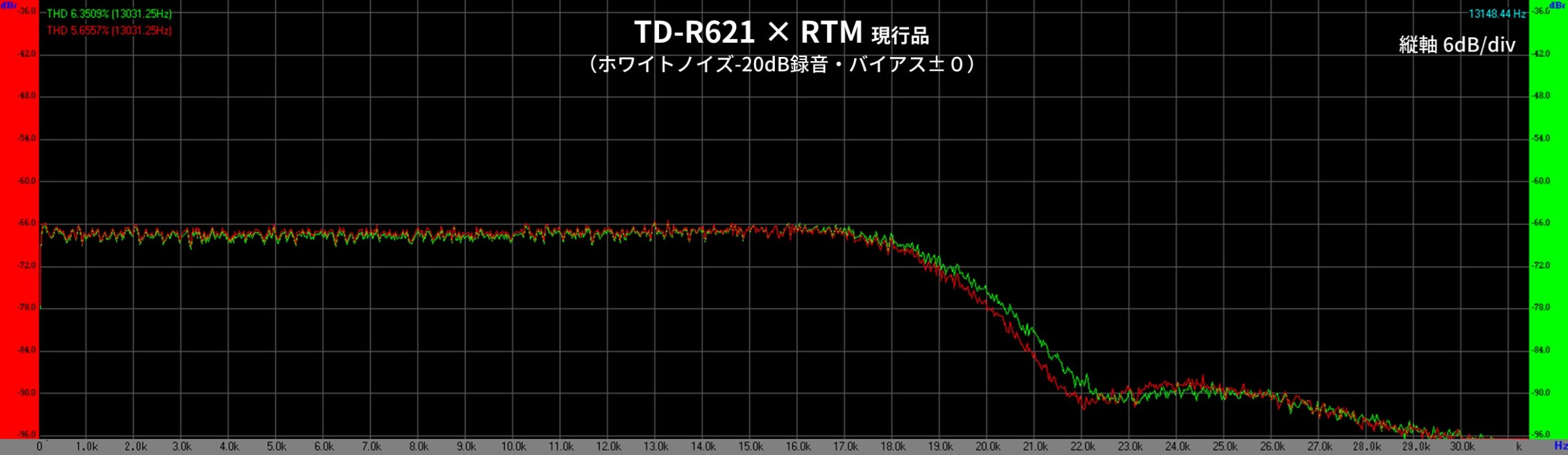
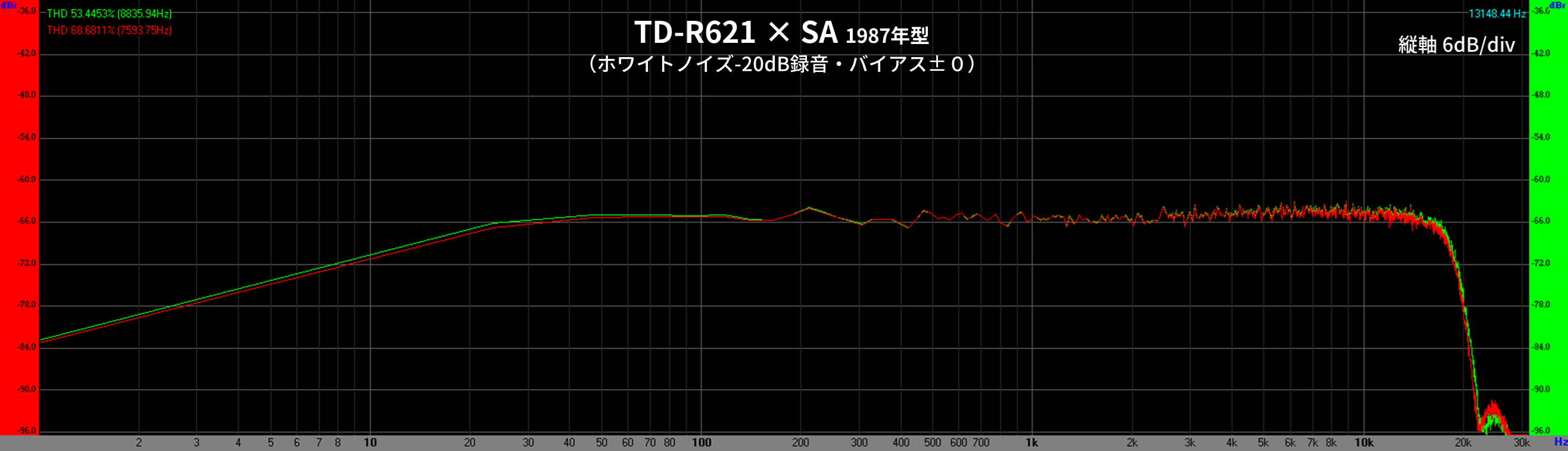
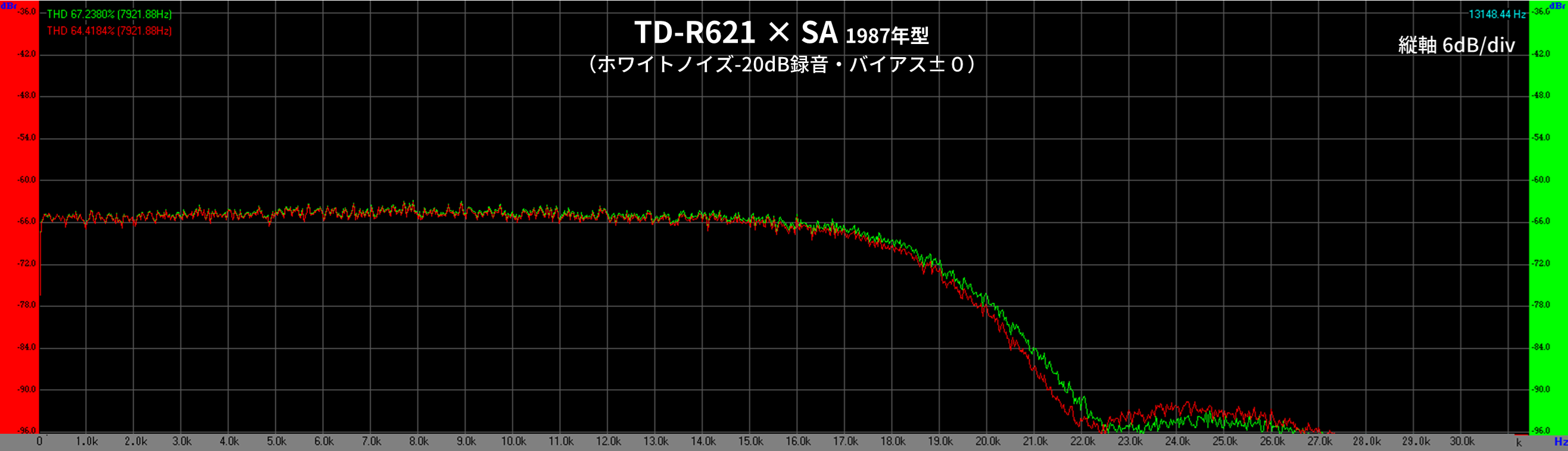
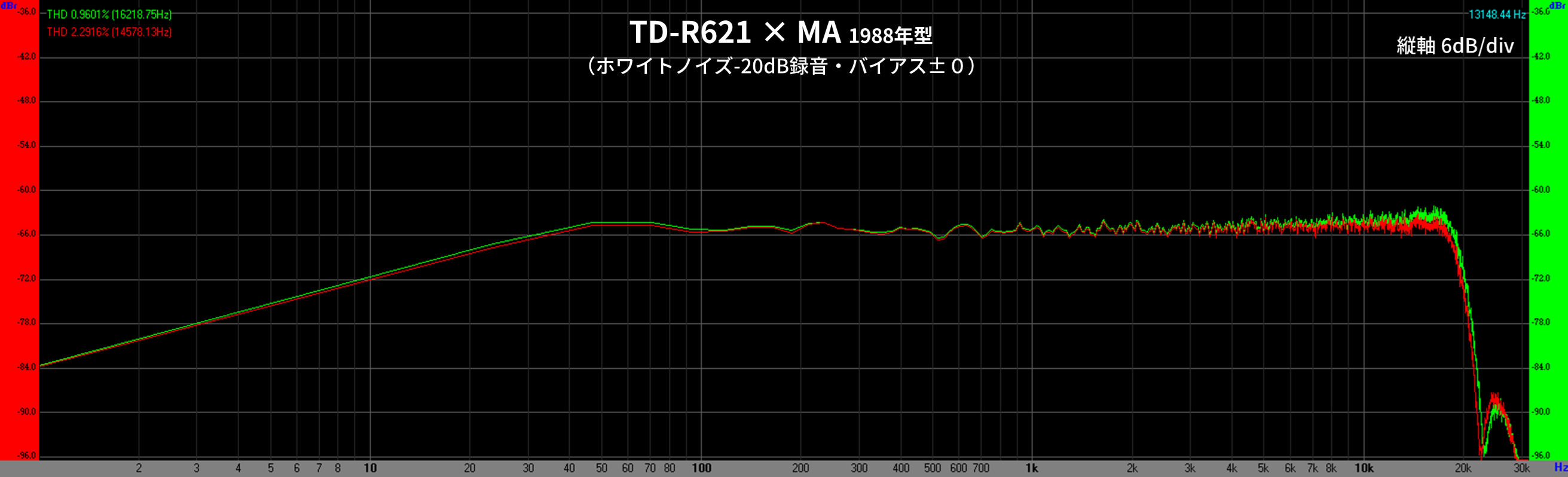
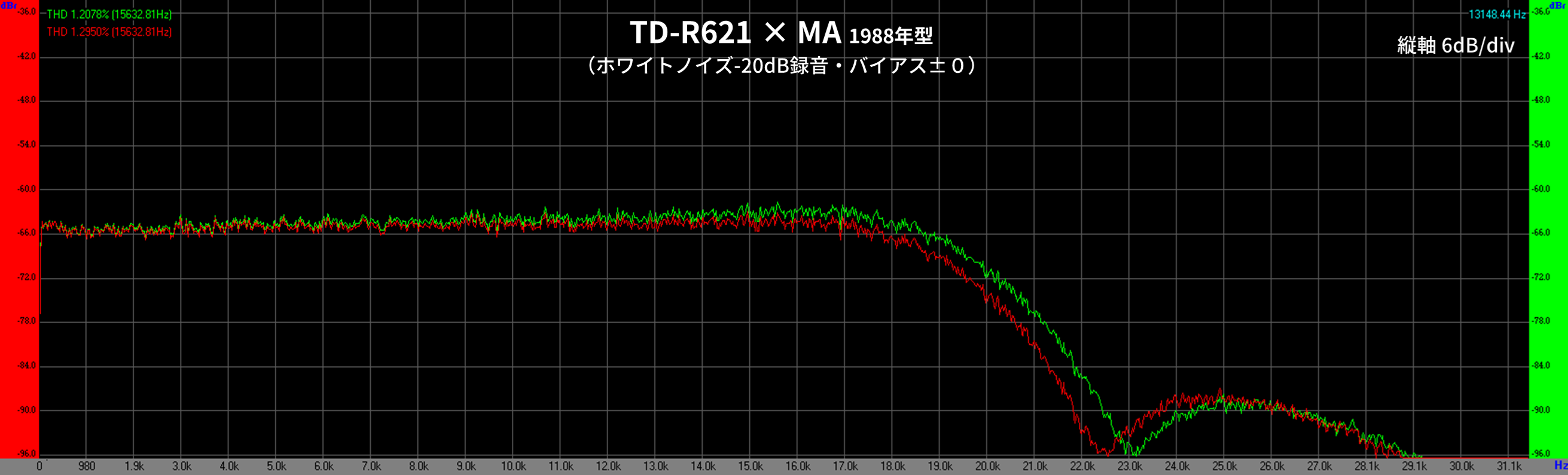
【TYPEⅠ】RTM (現行テープ)
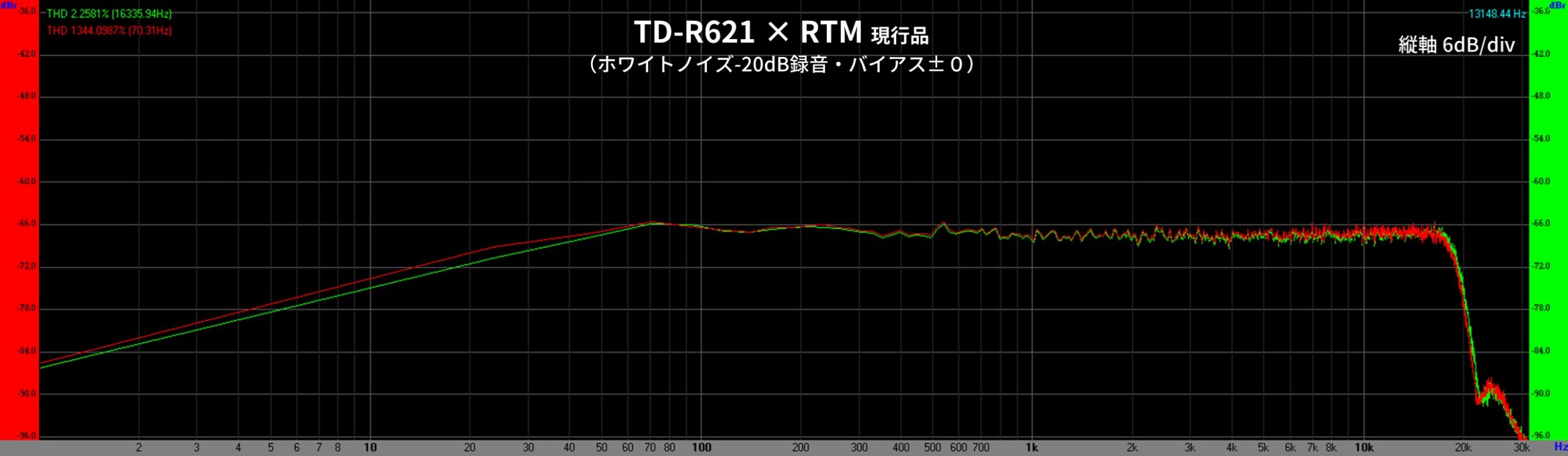
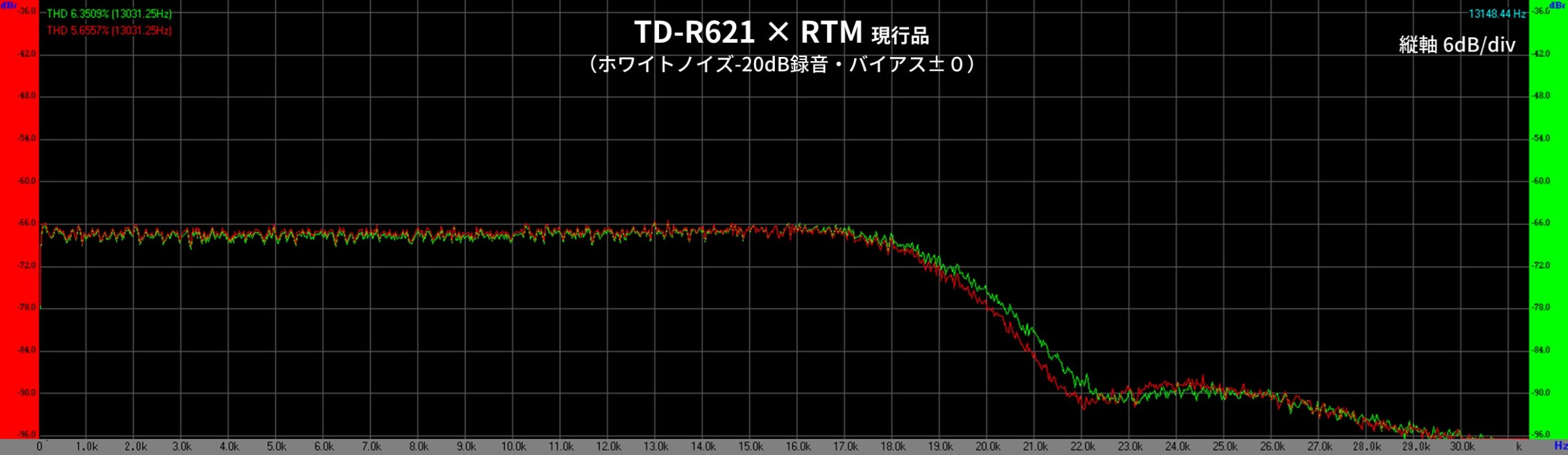
【TYPEⅡ】TDK SA (1987年型)
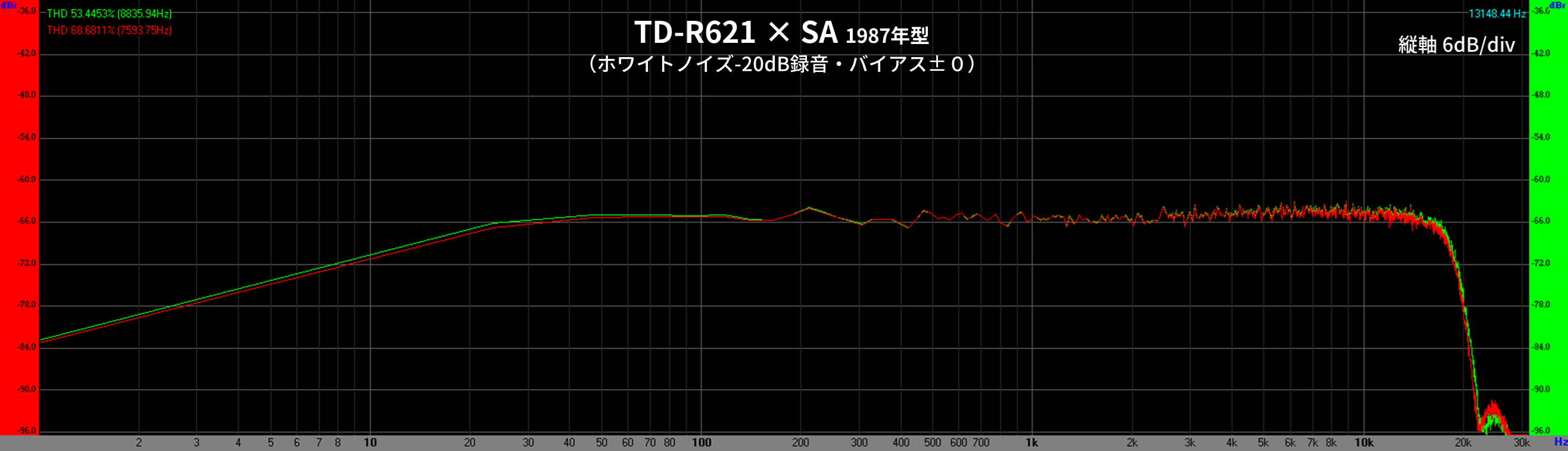
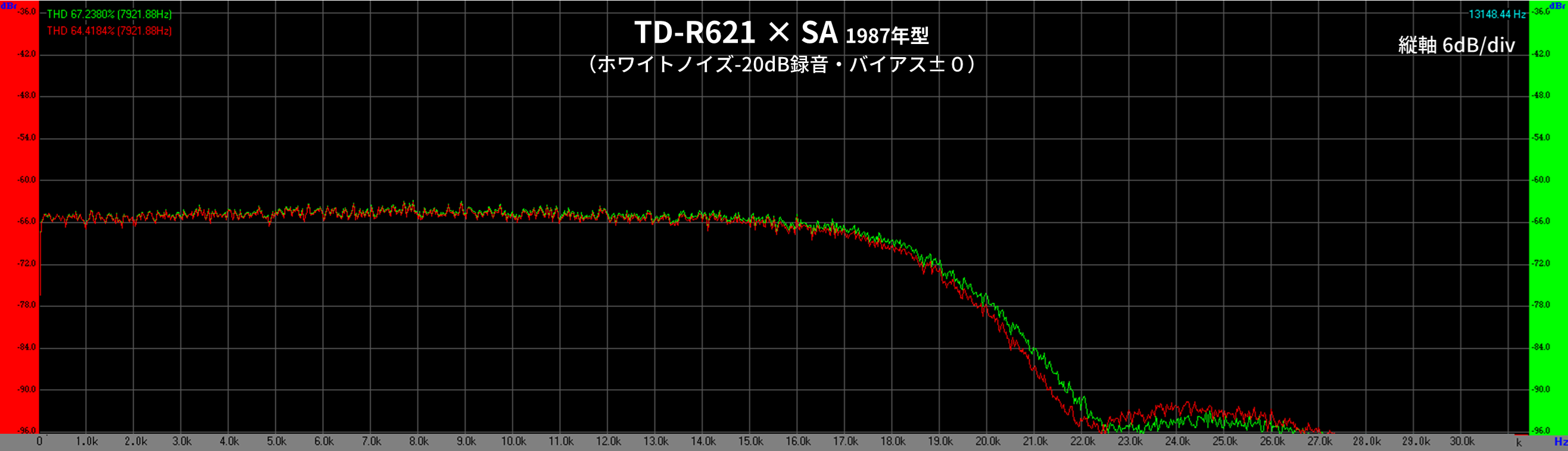
【TYPEⅣ】Nakamichi MA (1988年頃)
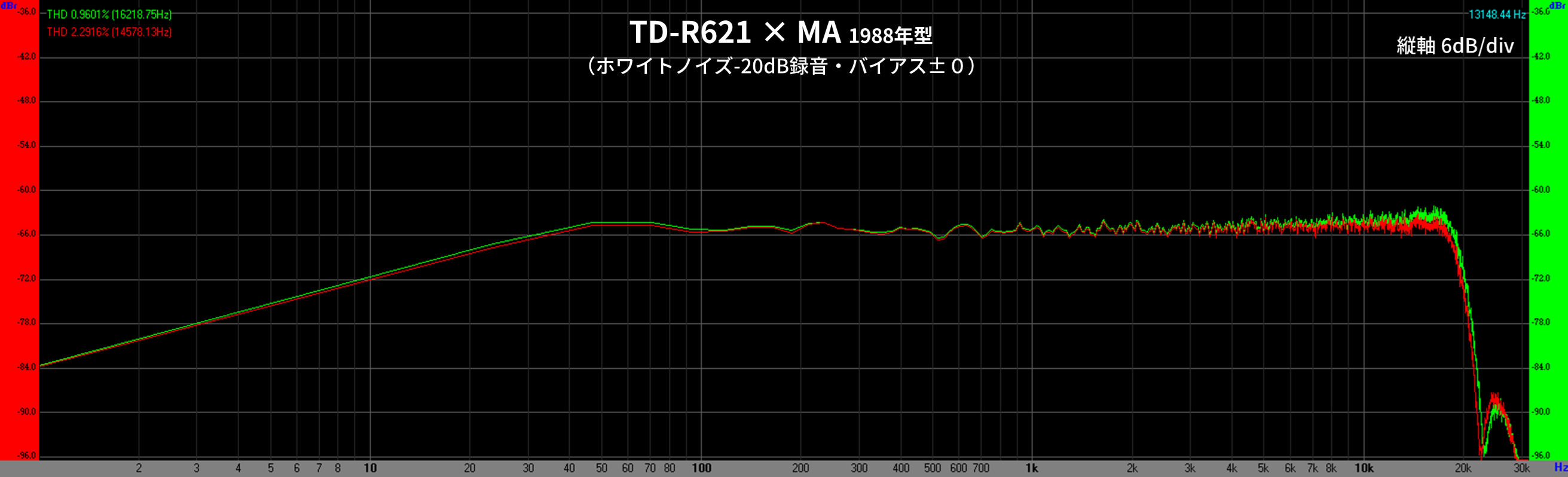
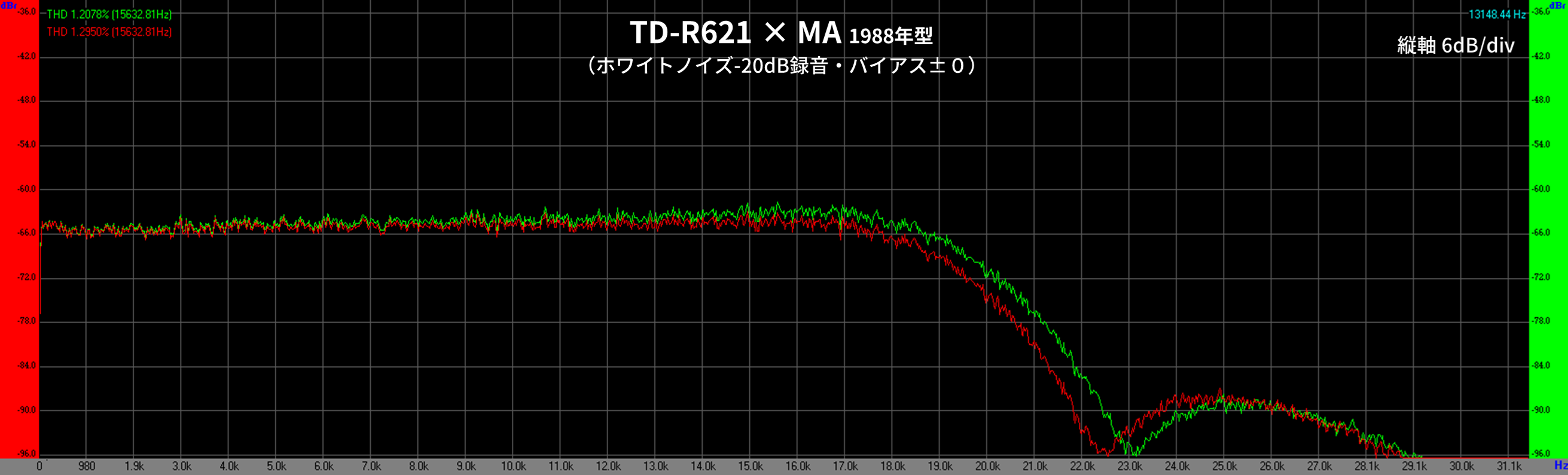
※ヘッドの状態やデッキの調整状態など個体差により、必ずしも同じ測定結果にはなりません。あくまで参考程度にお願いします。
これまでの作業実績
2024年6月 佐賀県 nao様